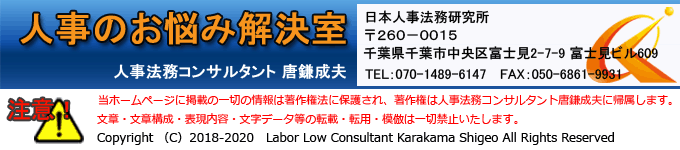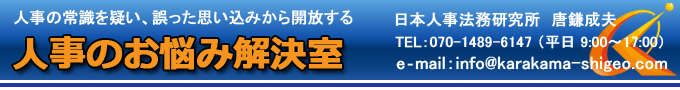
最終更新日:令和7年8月10日
振休は事前に振替休日を特定して振替出勤させる
のに対し、
代休は休日出勤をさせた事後に休日を付与する
という趣旨の解説をよく見かけるのですが、
「振休と代休では本質的に何が違うのか?」
と、深く考えていない自分に気が付きました。
振休と代休の違いについて、ゼロベースで検討してみたので、
その結果をシェアしたいと思います。
【振休と代休の基礎知識】
休日は、本来的には労働義務のない日ですが、
就業規則等に休日出勤ルールが規定されていたり、
予めルールがなくても、労使が合意したりすれば、
休日に出勤することになります。
休日の振り替えとは、
「事前に他の日を振替休日として指定した結果、
労働日に変化した日に振替出勤してもらう。」
ことを言います。
一方、代休制度は、
「とりあえず休日出勤をしてもらった後に、
その代替措置として休日を付与する。」ものです。
したがって、
振り替え制度による出勤日は休日労働でないないが、
代休を付与したとしても、休日労働の事実は変わらない
のですが、だからどうだって言うのでしょうか?
ちなみに、
代休は仕事が忙しければ、付与しなくてもオッケーです。
【法定休日の振休と代休は大違い】
休日には、
法定休日と所定休日の2種類があるので、
以下では、分けて詳細に検討してみます。
法定休日は、労働基準法により、
毎週1日(または4週4日)以上である必要があります。
したがって、例外的な4週4休日制である場合を除き、
法定休日を振り替える場合、振り替えた法定休日は同一週内
のなるべく近接した日である必要があります。
振り替えの場合、
振替出勤日は法定休日労働ではないため、
休日労働の割増賃金(いわゆる0.35部分)は支払い不要です。
振替休日を指定することなく法定休日に出勤させるためには、
36協定で休日労働する旨を協定し、届け出る必要があります。
この場合、代休を付与したところで、
法定休日労働の事実は変わることはないので、
法定休日労働の割増賃金を支払う必要があり、
その代休は、法定休日ではなくただの休日でしかない
と言えます。
したがって、
代休の付与日の対象期間には、労基法上の制限はなく、
民事的に良識の範囲内であればオッケーでしょう。
代休付与日が同一の賃金計算期間内であれば、
いわゆる1.0部分は相殺すれば、追加支給不要ですが、
次期以降の異なる賃金計算期間である場合は、
一旦、1.0を支給して、後日に1.0を控除するという
非常に煩雑な賃金処理をする必要があります。
【所定休日の振休と代休はほぼ一緒】
所定休日とは、法定休日以外のすべての休日を指します。
法定休日と異なり、所定休日の場合は、
振休でも代休でも、結果にほとんど違いが生じません。
振休も代休も対象期間に労基法上の制限はなく、
民事的に良識の範囲内であればオッケーです。
振替出勤や休日出勤により、週の法定労働時間を超えてしまう場合、
36協定で時間外労働する旨を協定し、届け出る必要がありますし、
時間外労働の割増賃金を支払う必要があることも一緒です。
いわゆる1.0部分の取り扱いも一緒になります。
【代休付与を就業規則に記載すべき】
ところで、皆さんの会社の就業規則には、
代休を付与することがあり、付与時は1.0部分は支払わない
旨の規定がありますでしょうか?
石嵜信憲弁護士のご著書「就業規則の法律実務(第6版)」に、
「・・・理論的には、代休として就労を免除したとしても
それは使用者の一方的な意思表示によるものにすぎず、
本来であれば反対債務である賃金支払義務は消滅しないため、
時給分を含めた1+0.35の賃金支払義務があるといえます。」
という記述があります。
この理論を考慮すると、
代休は就業規則に規定がなくても付与することは可能だが、
代休付与と1.0部分の賃金支払いを相殺するためには、
就業規則等により明確にしておいた方が無難と考えられます。
新たに就業規則に代休付与を規定することについては、
・代休を付与することは、疲労回復に繋がり労働者に有利益である。
・多くの企業では、代休を付与したら、1.0部分は支払っていない。
・賃金規程等に不就労控除が規定されていれば、合理性が高まる。
を考慮すると、不利益変更問題はそれほど心配しなくてよさそうです。