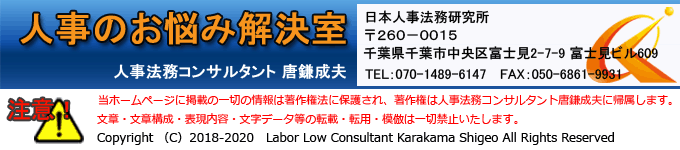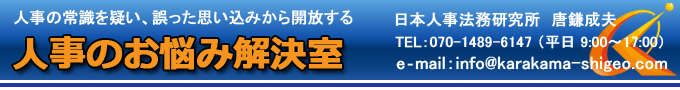
最低賃金法
(最低賃金額)
第三条 最低賃金額は、時間によつて定めるものとする。
平成30年12月現在、企業は、
千葉県の会社なら、時給895円以上
東京都の会社なら、時給985円以上
鹿児島県の会社なら、時給761円以上
の給料を従業員に支払わなければなりません。
最低賃金に違反しても
オマワリさんには怒られませんが、
労働基準監督官には、どつかれます。
出来高給は、
社員が自らの労働によって生み出した
仕事の量や成果に比例して支払う給料のことです。
厚生労働省が公表している
「平成26年就労条件総合調査」によれば、
給料総額の半分以上を出来高給が占めている企業の割合は約5%
だそうです。
それでは、
「時給200円+出来高給」
という労働契約は有効なのでしょうか?
検討してみましょう。
【論点①:最低賃金は、基本給などの固定的な賃金でなければならないか?】
最低賃金法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
三 賃金 労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。
労働基準法
(定義)
第十一条 この法律で賃金とは、
賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
以上のとおり、
最低賃金法上の「賃金」は、
労働基準法のそれと100%イコールです。
労働基準法では、賃金を
「名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」
と定義しています。
したがって、
最低賃金に含まれる賃金は、
基本給などの固定的な賃金である必要はない。
ということになります。
【論点②:最低賃金額に、「出来高給」を含めてよいか?】
最低賃金法
(最低賃金の効力)
第四条
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
最低賃金法施行規則
(算入しない賃金)
第一条 最低賃金法(以下「法」という。)第四条第三項第一号の
厚生労働省令で定める賃金は、
臨時に支払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
2 法第四条第三項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、
次のとおりとする。
一 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
二 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
三 午後十時から午前五時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち
通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
最低賃金に含めてはならない賃金を
わかりやすく表現するなら以下のとおり。
●結婚祝金、傷病見舞金などの臨時に支払われるもの
●夏季賞与、決算賞与
●残業手当
●休日出勤手当
●深夜労働の割増賃金
この他に、
都道府県地方最低賃金審議会において算入しないもの
とされる賃金として
●精皆勤手当、通勤手当および家族手当
があり、
これらも最低賃金に含めません。
出来高給は、
上記のいずれの賃金にも該当しないため、
最低賃金額に含めてよいことになります。
【論点③:ウッカリすると最低賃金を下回り「そうな」労働契約は有効か?】
事例の労働契約を単純に読むと、
「出来高ゼロのときは、給料は時給200円ぽっちり」
という解釈ができそうですが、
果たして、
ウッカリすると最低賃金を下回り「そうな」労働契約は有効なのでしょうか?
最低賃金法
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で
最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、
その部分については無効とする。
この場合において、無効となつた部分は、
最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
事例の労働契約は「時給200円+出来高給」
であり、
出来高給の額によっては最低賃金額以上となるため、
明らかに「最低賃金額に達しない」労働契約ではありません。
最低賃金法は、
実態として、最低賃金額以上の賃金を支払う。
ことを経営者に強要しているのであって、
明らかに「最低賃金額に達しない」労働契約でない限り、
その労働契約は最低賃金法違反として無効になることはありません。
【本事例についての具体策】
労働基準法
(出来高払制の保障給)
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、
使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
「時給200円+出来高給」という労働契約は、
実態として、最低賃金額以上の賃金を支払っていれば、
最低賃金法上、有効であり問題ありませんが、
労働基準法第27条の趣旨を踏まえるならば、
「出来高給は、最低賃金額を考慮して、決定する。」
とか、
「賃金が最低賃金額に満たない場合は、労働時間に応じた保障給を支給する。」
などの保障規定は、明示しておくべきでしょう。
また、以下の点についても留意しましょう。
●出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、
当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した
総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、
最低賃金額と比較する必要がある。
●「一月をこえない期間ごとに支払われる賃金」である必要があり、
2ヶ月に1回支給する出来高給は、最低賃金に含まれなくなってしまう。
●100%出来高給という労働契約であっても、
最低賃金を保障している限りにおいて、
その労働契約は有効である。
ちなみに、
最低賃金法では、
「所定労働時間をこえる時間の労働」と「所定労働日以外の日の労働」
は何故か算定の対象外なので、
法定労働時間内かつ所定時間外労働に対する賃金として、
一定月額の手当を支給する場合、
不当に低額でなければ、労働基準法および最低賃金法にも抵触しない
と考えられます。
一、所定労働時間が一日七時間である事業場において、
所定労働時間を超え、法定労働時間に至るまでの所定時間外労働に対する賃金として、
本給の外に一定月額の手当を定め
個々の労働者が所定時間外労働をすると否とにかかわらず
これを支給することはその手当の金額が不当に低額でない限り差し支えない。
二、右一の手当ては、
法三十七条にいう通常の労働時間の賃金とは認められないから、
同条の規定による割増賃金の基礎に算入しなくても差し支えない。
(昭和29.7.8 基発364号、昭和63.3.14 基発150号)
トップページへ戻る。