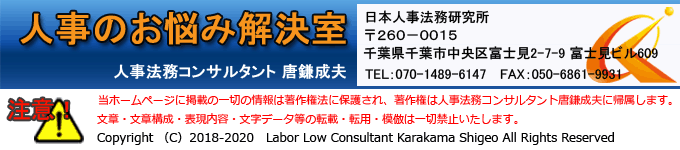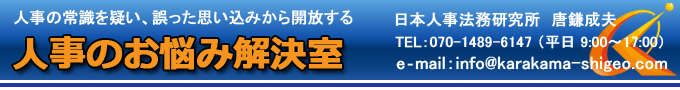
最終更新日:令和7年8月4日
基本給とは以下の3つに大別されるとされています。
・属人給:年齢、勤続年数、学歴等により決定
・仕事給:職務、職能遂行能力、職種等により決定
・総合決定給:属人給と仕事給を総合勘案して決定
中規模以上の企業では、
人事評価制度に属人給や仕事給の等級等を決めておき、
それに当て嵌めて機械的に基本給を決定していると思います。
一方、中小零細企業では、
人事評価制度なんてものは一切存在せず、
社長が直感と経験で何となく決めている、
どんぶり勘定という名の総合決定給の基本給が多い
のではないでしょうか?
ただし、いくらどんぶり勘定と言っても、
労働契約を締結する際(働き始める前の入社時)に、
基本給の金額は予め確定しておくのが常識ですよね?
ですが、ここでは常識を疑うこととし、
毎月、社長が社員の働きぶりを評価して、どんぶり勘定で決定する基本給は合法か?
について検証してみたいと思います。
【基本給は法的定義はなく、社会の共通認識でしかない】
労働基準法や最低賃金法には、
「賃金はキッチリ支払え!」とは書いてありますが、
「基本給を支払え!」とは書かれていません。
カラカマの知る限りではありますが、
基本給について定義している労働法令は存在せず、
労働基準法においても、唯一施行規則第54条に
「基本給、手当その他賃金の種類毎にその額を賃金台帳に記入せよ。」
と書かれているのみです。
日本経団連出版の「人事・労務用語辞典(第6版)」によれば、
「賃金を基本的部分と付加的部分に分けた場合、前者を基本給という。」
とされており、これが日本社会の共通認識となっているだけと言えそうです。
【どんぶり勘定の基本給は、労基法的には賞与である】
労働基準法第24条により、
賃金は、毎月支給するのが原則ですが、
毎月支給をしなくてもよい例外的な賃金の1つとして、
「賞与」があります。
賞与については、
旧労働省の通達に以下の定義が示されています。
賞与とは、定期又は臨時に、
原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、
その支給額が予め確定されていないものをいうこと。
定期的に支給され、かつその支給額が確定しているものは、
名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさないこと。
上記を踏まえ、
賞与の特徴をまとめるならば以下のとおり。
・定期または臨時に支給される。
・原則として労働者の勤務成績に応じて支給される。
・その支給額が予め確定されていない。
今回のテーマは、
「毎月、社長が社員の働きぶりを評価して、どんぶり勘定で決定する基本給」
なので、
・毎月支給⇒定期に支給される。
・社長が社員の働きぶりを評価⇒労働者の勤務成績に応じて支給される。
・どんぶり勘定で決定⇒支給額が予め確定されていない。
と考えられるとすれば、
本件の基本給は、
労働基準法や最低賃金法上、賞与と取り扱うべき
ことになります。
【予め確定されていない所定労働時間はNG】
ちょっと脱線しますが、
「始業・終業時刻は、都度毎朝社長が決定する。」のように
所定労働時間を予め確定しないことは合法でしょうか?
所定労働時間が確定していないと、
最低賃金の検証時や割増賃金単価算出時に困ってしまいます。
また、
労働基準法第15条に労働条件の明示義務が規定されており、
明示しなければならない事項が列挙されています。
始業および終業の時刻、休憩時間、休日および休暇が、
明示事項とされていることも考え合わせると、
どんぶり的所定労働時間はマズいでしょう。
賃金の決定、計算および支払の方法も明示事項ですが、
「基本給は、毎月社長が勤務成績を評価して決定する。」
とでもしておけば、今回の基本給は問題なさそうです。
【具体的な支給方法を考えてみる】
完全どんぶり勘定の基本給の支給方法を
マジメに考えてみました。
1.毎月支給する。
労働基準法上、賞与は毎月支給する義務はありませんが、
最低賃金法上、一月をこえる期間ごとに支払われる賃金は、
最低賃金計算時に算入できないので、毎月支給すべきです。
2.出来高払制の保障給を規定しておく。
出来高払制その他の請負制で使用する場合、
一定額の保障をしなければなりません(労基法第27条)。
労働基準法コンメンタール上巻に保障額の目安として、
少なくとも平均賃金の60%程度とされていますが、
あくまで行政が示した目安でしかありません。
最低賃金額以上は支払う必要があるので、
「基本給は最低賃金額以上を保障する。
と規定しておけばよいでしょう。
3.割増賃金の1.0部分は基本給に含まれる。
請負給に係る割増賃金のうち、
いわゆる1.0部分は請負給側で支払い済みとなります。
したがって、今回の基本給の場合の残業代は、
時間外労働時間数×(基本給額÷総労働時間)×割増率(0.25〜0.5)
で計算すればよいでしょう。
【結論】
マジメに検証した結果、
労働法的には、今回の基本給はあり得る
とカラカマは考えます。
ただし、民事で争った場合は、
公序良俗違反等で99.9%社長が負けると思われるので、
超カリスマ経営者のような自負でもない限り、
オススメしませんが・・・。