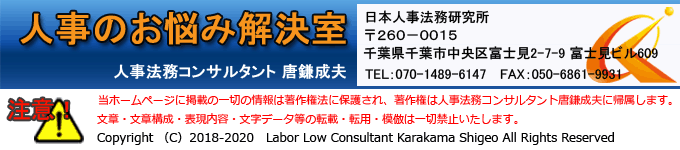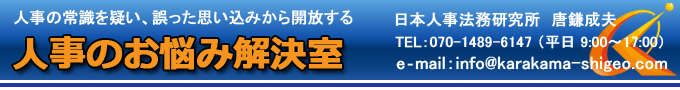
最終更新日:令和7年8月10日
平成30年1月に厚生労働省が、
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
を公表してから今年で7年目となり、すっかり、
副業・兼業は珍しくなくなったと感じています。
政府が副業・兼業を推奨している目的は、
働き方の多様化や人材の流動化の促進
だそうです。
・・・ですが、
中小企業における社員の副業は、
・受注量の低下により工場の稼働が減って収入減。
・残業時間の上限規制で残業手当が減って収入減。
等、収入増を目的とした切実なものがほとんどではないでしょうか。
ここでは、
中小企業は社員の副業にどのように対応すべきか?
について考えてみたいと思います。
【就業規則に「副業は許可制である」旨を明記する】
就業規則の服務規律に
「許可なく他の会社等の業務に従事したり自己の営業を行ったりしないこと。」
という趣旨の規定を設け、
社員に対し、副業を希望する時は会社に事前に相談する
義務を課しておくべきです。
【副業の事実を把握したら、面談をする】
当人から申し出や、他の社員からの通報により、
会社が社員の副業の事実を把握した場合は、
厚生労働省のガイドラインに記載があるように
・労務提供上の支障がある場合
・業務上の秘密が漏洩する場合
・競業により自社の利益が害される場合
・自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
に該当するような会社に良くない影響がないか?
を確認する必要があるので、
管理者による面談を行い、確認事項を記録として残す
ことをオススメします。
具体的には、副業先や業務内容および
労働時間(出勤日数、所定労働時間、始業・終業時刻、残業の有無等)
を確認すべきでしょう。
同意書等の書類の提出を求めるか?ですが、
ある程度の企業秘密を保持している上級職の社員が
副業する場合は必要だと考えますが、
企業秘密を保持しない現場担当等の一般社員であれば、
面談記録を残せば事足りるのではないでしょうか。
【日々の健康に配慮する】
f副業の目的が、収入減を補う収入増だった場合は、
会社は合理的な理由がない限り、副業を許可せざるを得ないでしょう。
面談の上で副業を認めた場合、それ以降に会社が行うべきは、
・日々の健康に配慮する。
・最低限度の労働時間管理を行う。
の2点と考えます。
まず、健康への配慮ですが、
社員が副業していようがいまいが、
会社にはすべての社員の安全と健康に配慮する義務があるので、
寝不足や体調不良の社員が居ないか?
を管理者が日々確認を怠ってはならないことは
言うまでもありません。
副業をしている社員の直接の上司には、
部下が副業している事実を伝え、
それなりの配慮をするように指示しましょう。
一方で、社員(=労働者)には、
債務の本旨に従った労務の提供義務
があります。
分かりやすく言えば、
・体調を整えて出勤する。
・会社の指示に従う。
・就業時間中は業務に専念する。
等の義務があるということです。
副業する社員自身も、
「長時間労働等により疲労を蓄積させないよう体調管理をする。」
ことを自覚していただく必要があります。
同意書等の書類の提出を求める場合は、
自己の体調管理義務も記載しておくとよいでしょう。
【労働時間管理はケースバイケースで対応する】
次に、やっかいな労働時間管理ですが、
自社での残業の程度によって対応が異なります。
【ケース1】自社での時間外労働・休日出勤がゼロ
この場合は、労働時間管理は一切不要です。
何故なら、
・自社での労働が長時間労働の原因になることはまずない。
・割増賃金の問題が一切生じない。
からです。
【ケース2】自社での時間外労働・休日出勤が少しある(月20時間未満くらい?)
この場合も、労働時間管理は不要と考えます。
何故なら、
・自社での労働が長時間労働の原因になるとは考え難い。
・未払い残業代があったとしても少額であり、大事には至らない。
からです。
未払い残業代についてですが、
自社での時間外労働や休日出勤が
結果として法定時間外労働や法定休日出勤だった場合でも
割増賃金の1.25〜1.35のうち、1.0部分を支払っていれば、
未払い分は割増部分の0.25〜0.35だけということになります。
1日6時間、時給1,000円のパート社員に月20時間の残業があり、
法定内の残業代として、20,000円を支払っていたが、
実は副業先の労働時間と通算すると法定時間外労働だった場合、
250円×20時間=5,000円の未払い残業代となります。
現在の賃金請求権の時効は3年なので、
塵も積もれば山となりますが、
会社が傾くような多額の未払い残業代にはならないと思います。
【ケース3】自社での時間外労働・休日出勤が多い
この場合は、ケースバイケースの対応となります。
・自社での残業時間を減らす〜禁止する。
・社員自身で労働時間管理をしてもらう。
・そもそも、副業を認めない。
等が考えられます。
令和6年9月20日付けの日本経済新聞において、
「労働時間の通算管理を規定する労働基準法の
解釈変更を出すか、法改正で対応することになる
見通し」との報道がなされており。
厚生労働省の動きに注視しておく必要があります。