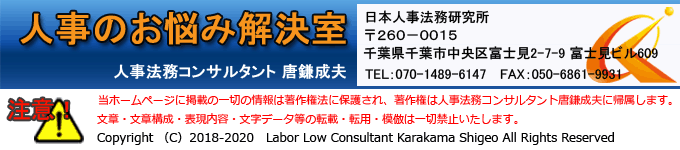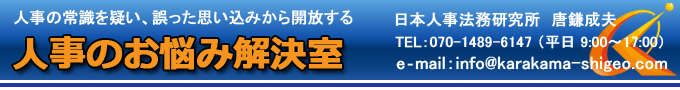
最終更新日:令和7年8月10日
社労士が企業から新規に顧問のご依頼を受けたり、
社員さんが初めて人事関係の部署に配置転換されたとき、
労働・社会保険の適用状況を確認すべきです。
確認の結果、適用状況が不適切と考えられる場合は、
会社の実情を考慮して最適な状態に改善したいところです。
<A株式会社の事例>
令和元年、B市でスーパー(1号店。社員数70名)を開業。
令和3年、B市の隣のC市に2号店(社員数60名)を出店。
令和4年、1号店内で不動産屋(社員数6名)を開始。
令和5年、2号店内でラーメン屋(社員数3名)を開始。
・1号店内には、本社機能としての事務所(社員数15名)がある。
・1号店および2号店の社員の労務管理は、まとめて本社で行っている。
・不動産屋は他と人事異動がないが、1・2号店間では常態として人事異動がある。
ここでは、
A株式会社の労働・社会保険法の適用単位はどうすべきか?
について考えてみたいと思います。
【労働基準法】
36協定の締結や就業規則の作成等は、
「事業場」ごとに行う必要があるため、
事業場をどう区分するか?は慎重に判断すべき
重要事項と言えます。
事業場とは、「本法の適用事業として決定される単位である。」
とされており、以下のとおりの概念であると言えます。
・事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗の如く
一定の場所において相関連する組織のもとに業として
継続的に行われる「作業の一体」をいう。
⇒事業とは、「組織的な作業の一体」が単位である。
・原則として、場所的観念によって決定する。
⇒1号店と2号店は、場所的に独立しているので、
原則として、別個の事業と言える。
・同一の場所にあっても、著しく異なる業を行う
複数の部門がある場合、独立した事業とすることが
適切なときがある。
ただし、個々の労働者の業務による分割は認められない。
⇒同一の場所にあるものの、著しく異なる業を行っているので、
小売業の1号店と本社機能である事務所と不動産屋は、
それぞれ独立した事業と考えるべき。
一方、2号店のスーパー(小売業)とラーメン屋(飲食業)は、
同じ食べ物を扱っており、「著しく異なる」とまでは言えなくもない。
・場所的に独立していても、規模が小さい場合で、
独立した事業として取り扱うべきでないときは
直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う。
⇒2号店は社員が60名在籍していることを考慮すると
小規模とは考え難いので、独立した事業と考えるべき。
以上を考慮すると、A株式会社は、
1.本社事務所
2.スーパー1号店
3.不動産屋
4.ラーメン屋含むスーパー2号店
の4事業に区分するか、
ラーメン屋を2号店とは別事業と考え、
5事業に区分すべきと考えられます。
1号店と2号店が一の事業として適用できれば、
36協定届や就業規則変更届等、本法関連の届け出先は、
一つの労働基準監督署だけとなるので、
事務処理の労力を軽減できます。
1号店があるB市はD労働基準監督署管轄、
2号店があるC市はE労働基準監督署管轄であった場合は、
1号店と2号店をまとめて一事業と取り扱うことは
まず無理でしょう。
しかし、
1号店と2号店が同じ市内に所在しており、
管轄する労働基準監督署が同じである場合は、
1号店と2号店をまとめて一事業として取り扱っても、
監督官がウッカリ見逃せば、
発覚するまで何事もなく時が過ぎていくことになるでしょう。
なお、
事業や事業場と異なる概念として「事業主」がありますが、
事業主とは、個人経営なら自然人としての社長本人、
法人であれば、法人そのものを指します。
【労働安全衛生法】
労働安全衛生法は、労働基準法第5章を中核として、
昭和47年に制定された法律であり、本法の適用単位は、
労働基準法の事業場とまったく同じです。
・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
労働安全衛生法の施行について (昭和47年9月18日 発基第91号)
三 事業場の範囲
この法律は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、
安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、
この法律による事業場の適用単位の考え方は、
労働基準法における考え方と同一である。
・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
また、
本法の「事業者」も労働基準法の「事業主」と
イコールの関係にあります。
本法に定める衛生管理者や産業医や衛生委員会は、
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、
選任・設置しなければならないとされています。
1号店と2号店が一の事業として適用できれば、
衛生管理者は1人、衛生委員会も1つで事足りますが、
別々の事業となる場合は、それぞれで配置する必要が
あります。
ストレスチェックは、
常時50人未満の労働者を使用する事業「場」では努力義務
ですが、その検査結果等報告書の提出義務は、
常時50人以上の労働者を使用する事業「者」が対象なので、
紛らわしいです。
ちなみに、
定期健康診断結果報告書の提出義務も、
常時50人以上の労働者を使用する事業「者」が対象です。
【労災保険法】
本法の適用単位としての事業について、
「一定の場所において、
一定の組織の下に相関連して行われる『作業の一体』は、
原則として一の事業として取り扱う。」
と定義しており、労働基準法の事業と99%同じ文言です。
36協定届や就業規則変更届には、
労働保険の保険関係成立届を提出すると振り出される
「労働保険番号」を記載することになっています。
このことからも、
本法と労働基準法および労働安全衛生法の適用単位は同一
といえます。
ただし、
本法と労働安全衛生法では、事業の種類の区分方法が異なる
ので混同しないように注意が必要です。
A株式会社の事業の種類とその労災保険率は、
以下のとおりです。
1.本社事務所 :その他各種事業⇒1000分の3
2.スーパー1号店:小売業 ⇒1000分の3
3.不動産屋 :不動産業 ⇒1000分の2.5
4.スーパー2号店:小売業 ⇒1000分の3
5.ラーメン屋 :飲食店 ⇒1000分の3
小売業と飲食店は、労災保険率表上、
「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」
という区分に属しているため、労災保険率は同じです。
同じ区分に属していることから推測するに、
小売業と飲食店は「著しく異なる事業」ではないと考えられるので、
ラーメン屋とスーパー2号店はまとめて一つの事業と
取り扱っても問題ないでしょう。
【労働保険徴収法】
労働保険徴収法は、
労災保険料と雇用保険料の納付ルールを定めた法律です。
労働保険徴収法には、
「メリット制」という制度があります。
メリット制は、事業におけるメリット収支率
(≒被災時の保険給付等の額÷収めた保険料額)により、
労災保険料率を最大で40%増減させる制度です。
メリット制には、規模要件があり、
一定人数以上の労働者を使用する事業に対して、
適用されます。
小売業の場合、
事業場の労働者数が100人以上の場合に
メリット制が適用されます。
労働保険徴収法には、
「継続事業の一括」という制度もあります。
「継続事業の一括」制度は、
事業主および行政の事務処理の便宜と簡素化を図るために
複数の事業所の労働保険料に係る事務処理をまとめちゃおう
というもので、以下の要件を満たす必要があります。
・事業主が同一人である。
・それぞれの事業が継続事業である。
・労災保険および雇用保険の成立形態が同じである。
・事業の種類が同じである。
一括する事業を「指定事業」、
一括される事業を「被一括事業」と呼びます。
継続事業の一括が認可された場合、
被一括事業の労働者も指定事業の労働者とみなして
メリット収支率を判定します。
カラカマは、
以下のメリット制と継続事業の一括の関係性を考慮した上で。
継続事業の一括を活用すべきと考えています。
1.メリット制を適用したくない場合は、労働者数を一定人数以下に抑えればよい。
2.メリット収支率を下げたい場合、分母である保険料を増やせばよい。継続事業の一括で対象労働者数を増やせば、保険料も増える。
3.メリット収支率の分子である保険給付等の額が多額となった結果、メリット制により労働保険料率が上昇した場合、対象労働者数が多いほど、支払う保険料総額も増えてしまう。
4.一括前の指定事業以外の事業に係る保険給付等の額は、一括後における指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入されない。
5.被一括時の被一括事業に係る保険給付等の額は、一括取り消しにより独立した事業に係るメリット収支率の算定基礎に算入されない。
事例のA株式会社の場合、
1号店と2号店はいずれも事業場の労働者数が100人
に満たない為、単独ではメリット制の対象となりません。
しかし、継続事業の一括により、
1号店を指定事業、2号店を被一括事業にすれば、
事業場の労働者数が100人を超えるので、
メリット制が適用されることになります。
たとえば、
A株式会社が高齢者を積極的に採用していく方針であり、
高齢者特有の怪我(些細な段差でコケる等)が多いと考えれば、
メリット制が適用されないように一括しない方が得策でしょう。
【雇用保険法】
雇用保険法の「事業」は、
労働基準法や労災保険法の「作業の一体」という定義と
若干異なり、「一体的な経営活動」と定義されています。
雇用保険法は、事業所単位で適用されますが、
「事業」が経営活動単位の機能面を意味するのに対し、
「事業所」はその物的な存在の面を意味するとされており、
事業所の単位と事業の単位は、本来同一のものであり、
雇用保険法上の事業所の単位と徴収法施行規則上の事業場の単位は、
原則として一致すると業務取扱要領に記載されています。
雇用保険法には、
「事業所非該当承認」という制度があります。
「事業所非該当承認」制度は、
一の経営組織としての独立性を有しない施設につき
一の事業所として取り扱わないことを行政に承認してもらう
というもので、以下の要件を満たす必要があります。
・場所的に他の(主たる)事務所から独立していること。
・経営(または業務)単位としてある程度の独立性を有していること。
・一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
ただし、「上記にかかわらず、
その施設の従業員数(被保険者とならない者を含む。)
が相当程度多い場合(50名以上をいう。)には、
一般的には、一の経営組織としてある程度の独立性を有するものであり、
一の事業所として取り扱うべき場合が多い。」とされています。
事例のA株式会社の場合、
令和3年の2号店出店時に事業所非該当承認を受けるか
一旦、出店時は独立した事業所として届け出て、
雇用保険の事業所番号を付与されたとしても、
事後に事業所非該当承認を受けることができれば、
1号店と2号店は、一つの事業所として適用でき、
雇用保険の事業所番号は一つとなります。
ただし、2号店の社員数が50人以上なので、
事業所非該当申請が承認されないかもしれません。
2号店出店時は独立した事業所として届け出て、
その後に労働保険徴収法の継続事業の一括をした場合は、
2号店には、1号店の労働保険番号に続く
一括整理番号が付与されます。
ただし、事業所非該当承認を受けていない場合、
雇用保険としては別々の事業所のままで変わらず、
雇用保険の事業所番号も異なるので、店舗を跨いだ
人事異動があった場合、転勤届を提出する必要があります。
また、
「継続事業の一括の認可がなされている施設については、
当該施設は、認可の前提として徴収法施行規則上の
事業場として認められているものであるから、
原則として、事業所非該当の取扱いを行わない」
とされていることに留意しましょう。
令和4年の不動産屋開始時は、
独立した事業所として届け出るべきですが、
令和5年のラーメン屋開始時は、
2号店の一部と考えれば何もしなくてもよい
と考えます。
以上が、
雇用保険法的に正しい事務処理となりますが、
実務では結構いい加減なようです。
たとえば、1号店と2号店が同じ市内にあり、
管轄するハローワークが同じ場合は、
2号店開始時に適用事業所設置届を出さずに、
1号店でまとめて事務処理を行っていても、
何事もなく時が過ぎていくようです。
雇用保険料率は、
農林水産業、清酒製造業および建設業以外の業種
はすべて一緒なので、上記3業種が混じっていなければ、
雇用保険の事業所は、まとめて一つでも大丈夫かもしれません。
なお、雇用関係助成金は、
雇用保険の適用事業所単位で運用されており、
1支給年度の対象者数に上限を設けていたり、
特定の業種を対象にしていたりするので、
これらも考慮た上で適用単位を決定したいところです。
【健康保険法と厚生年金保険法】
健康保険法と厚生年金保険法=狭義の社会保険の
適用単位は、「常時従業員を使用する事業所」であり、
法律上は、以下のように規定されています。
「当該事業所を独立単位として扱うべきか否かは、
これに使用される被保険者の身分関係、指揮監督、
報酬の支払い等直接の人事管理を受けるか否か等に
基づき、社会通念上決定すべきものである。」
「一つの事業所において明らかに異種の事業が
併存的に行われるときは、それぞれの事業毎に適用を決定し、
又一つの事業が他の事業に従属附帯し、
包括して一つの事業を行うものと認められるときは、
主たる事業と一体的にその適用を決定することが適当である。」
平成14年の法改正時に
事業主が同一の場合、厚生労働大臣の承認を受ければ、
複数の適用事業を一つの適用事業所とみなす
一括適用ルールが導入されましたが、
実務的には使い勝手がよくない制度でした。
そこで、平成18年の行政通達により、
「同一の企業において本社、支店等の複数の適用事業所
がある場合の社会保険の適用については、
被保険者が勤務する事業所に関わらず、
その者に対する人事、労務及び給与の管理がなされている
事業所において適用すること。」
という実務的取り扱いがルール化されました。
事例のA株式会社の場合、
すべての事業の人事管理が本社にて行われているので、
まとめて1つの適用事業所とすれば問題ないでしょう。