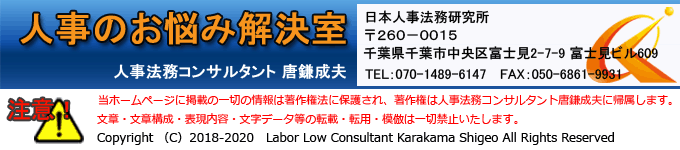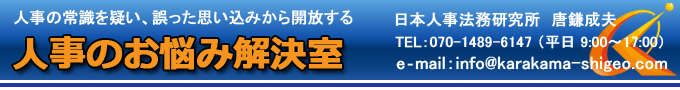
最終更新日:令和7年8月10日
先日、フレックスタイムについて調べている際に
官公庁(国家公務員)で柔軟な働き方ができる制度
の導入が進んでいることに気が付きました。
省庁の長が公務の運営に支障がないと認める場合、
・フレックスタイムで1日の勤務時間を調整可能。
・休憩の時刻(位置)と時間(長さ)を調整可能。
・省庁統一のガイドラインに則りテレワークも可能。
とされており、令和7年度からは
フレックスタイムを利用すれば週休3日も可能
となるそうです・・・。
<仮想事例>
物流会社のA社では、
自社製の荷物管理システムを構築するITエンジニアを探していました。
そんなA社のB社長はある日偶然にも、
伝説のITエンジニアC氏(66歳)と知り合いになりました。
B社長がC氏に、
荷物管理システム構築の件を打診してみたところ、
「6ヶ月後の完成でよければ、超チョロい仕事やね。」
というではありませんか!!!
C氏はその仕事を受けるにあたり、
「その仕事には合計600時間くらいあれば十分だが、
自宅でできるだけ自由に健康に留意して仕事がしたい。」
という要望をB社長に伝えました。
そこで、B社長とC氏が相談した結果、
・6ヶ月間の有期雇用契約
・業務内容は、通常600時間程度掛かるプログラミング業務
・完全在宅勤務
・1ヶ月間の所定労働時間は、100時間
・始業および終業時刻は完全に自由。ただし、深夜時間帯の勤務は厳禁
・法定労働時間(1日8時間、週40時間)を厳守。時間外労働厳禁
・休憩は労基法の45〜60分ルール以上であれば、時刻・時間は自由
・週に1日以上の休日を取れば、勤務日数も自由
・給与は、月給30万円(最低賃金以上)
という労働条件で合意に至りました・・・。
ここでは、
健康に留意したうえで、法的にどこまで自由に働くことができるか?
というギモンについて、上記事例を題材に
フレックスタイム制または事業場外のみなし労働時間制
を採用したらどうなるか?を検討してみたいと思います。
なお、
事例のような働き方であれば、
本来的には専門業務型裁量労働制が王道と思われますが、
今回は王道は無視しますので、あしからず。
<フレックスタイム制を採用した場合>
フレックスタイム制は、
始業および終業時刻を社員の決定にゆだねる制度であり、
在宅勤務になじみやすい制度と言えます。
労働基準法第32条の3に、
フレックスタイム制についての規定がありますが、
事例では法定労働時間(1日8時間、週40時間)を厳守するので、
同条の規制は受けず、同条が定める労使協定は不要です。
なぜなら、
同条はあくまで法定労働時間(1日8時間、週40時間)
を超えて働く場合に上限規制を解除するルールなので、
法定労働時間の範囲内で働く場合は、同条の規制は受けない
からです。
「労働基準法(厚生労働省労働基準局編)」
という書籍に
「本条(第32条の3)は、
禁止の解除を規定しているにすぎないので、
その性質上法違反の成立する余地はないが、
本条の要件を満たさないで
日又は週の法定労働時間を超えて労働させた場合には、
第32条違反として罰則の適用を受けることになる。」
とあることからも明らかです。
始業および終業時刻は、
労働基準法第15条により書面等により明示する必要がありますが、
「始業および終業時刻は社員の決定にゆだねる。」と明示すれば
問題ありません。
ただし、実務的には、
労働基準法第32条の3の労使協定で定めるべき事項
(たとえば、標準となる一日の労働時間)についても
就業規則に記載しておかないと機能不全に陥るでしょう。
フレックスタイム制であっても、
会社には社員の労働時間を適切に把握する義務はあります。
PCの使用記録等の客観的な記録により把握する方法もありますが、
いわゆる「中抜け時間」問題も考慮すると、
一日の終業時に、労働時間をメール等にて自己申告してもらって
把握するとよいのではないでしょうか。
<事業場外のみなし労働時間制を採用した場合>
事業場外のみなし労働時間制とは、
労働者が事業場外(≒上司の目の届かないところ)
で業務を行う場合、所定労働時間労働したとみなす制度
と言えます。
労働基準法第38条の2に、
事業場外のみなし労働時間制について規定されており、
労働時間を算定(把握)し難いときに限り適用できる
とされています。
在宅勤務における「労働時間を算定し難いとき」について、
より具体的には、厚生労働省が公表している
「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
に示されており、以下の2点のいずれも満たす場合には、
事業場外のみなし労働時間制度を適用することができるとされています。
・情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
・随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
事例の場合、各日の実際の労働時間にかかわらず、
1ヶ月間に100時間働いたものとみなすことになります。
事業場外のみなし労働時間制の場合、
会社には
労働基準法の「労働時間」は把握する義務がないのですが、
労働安全衛生法の「労働時間の状況」は把握する義務があります。
「労働時間の状況」は、「労働時間」とは異なる概念であり、
「労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったか?」
を把握することになります(異様にややこしいですね。)。
実務的には、フレックスタイム制と同様に
PCの使用記録等の客観的な記録により把握が原則ですが、
その日の労働時間の状況(始業・終業時刻)を翌労働日などに自己申告させる
方法が適当でしょう(行政通達(平成31年3月29日基発第0329号)参照。)。
<その他の論点>
●休憩
休憩は、
一斉付与を除外する労使協定を締結した上で、
労働時間の途中に労働時間に応じて45〜60分
以上休めば問題ないでしょう。
中抜け時間については、
テレワークガイドラインには、
中抜け時間を把握する場合⇒休憩時間と取り扱いOK
中抜け時間を把握しない場合⇒所定休憩時間休憩したものとみなす
という運用が示されています。
●休日
休日は、
労働基準法第15条により書面等により明示する必要がありますが、
あらかじめ休日を特定することが望ましいものの、
特定は義務ではないとされています。
したがって、
「休日は週に1回以上とし、社員の決定にゆだねる。」
と就業規則等に明示すれば問題ないことになります。
●あまりに自由過ぎると労働者性を否定されるかも?
労働基準法の保護対象である「労働者」とは、
会社の指揮命令を受けて働き、その対価としてお給料を貰う者
なので、あまりに野放しで自由に働ける労働条件の場合、
「自由なあなたは、もはや労働者ではない!」と判断されることがあります。
厚生労働省のホームページに
「在宅勤務者についての労働者性の判断について」
があり、参考になります。
労働者性を否定されると、
労災保険を利用することもできなくなります。
労災保険には、
労働者でない者も加入できる「特別加入」という制度があり、
令和6年11月1日から、すべてのフリーランスが対象者になりました。
事例程度の自由度であれば、
労働者性を否定されないと考えますが、
より自由な働き方を選択する場合には、
個人事業主として業務委託契約を締結し、特別加入しておく
とよいかもしれません。
厚生労働省は、
在宅勤務などテレワークで働く日に限ったフレックスタイム制
の導入を検討しているそうです。
健康を担保した上で、
自由な働き方を許容する社会になるとよいですね。