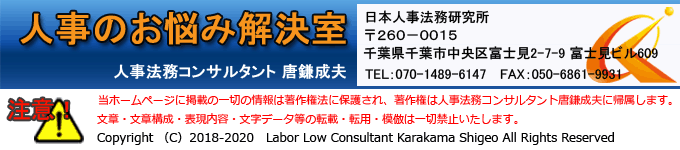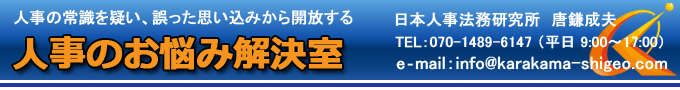
最終更新日:令和7年8月4日
日本国内に住所を有する75歳以上の者は、
生活保護受給者や日本国籍を有しない一部の者を除き、
強制的に後期高齢者医療制度に加入することになります。
75歳以降も働き続ける労働者が増えてきていることを考えれば、
人事を担当する上で、
後期高齢者医療制度の知識も必要となってくるでしょう。
ここでは、
高齢者の資産管理をするという視点から
後期高齢者医療制度の基礎知識について、
ご紹介したいと思います。
※千葉県における後期高齢者医療制度を調べたので、
他県では若干異なる場合があるのでご注意ください。
【ポイント1:保険料と窓口負担割合は、異なる所得基準で判断される】
後期高齢者医療制度に関係する出費は、
保険料と病院に行った際に支払う窓口負担
が考えられます。
保険料算定の基礎となる「賦課のもととなる所得金額」
のルールは、以下のとおりです。
・給与所得や公的年金所得等の総合課税分だけでなく、山林所得や株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税分も対象になる。
・退職所得並びに遺族年金、障害者年金および失業給付等の非課税所得は、含まれない。
・給与所得控除や公的年金所得控除等の個別の所得金額算出時に控除できるものは差し引かれる。
・合計した所得から差し引けるのは基礎控除の43万円のみであり、市町村民税算出時に控除できる社会保険料控除や生命保険料控除等は差し引かれない。
一方、
窓口負担割合判定の基礎となるのは「課税所得(課税標準)」であり、
上記の「賦課のもととなる所得金額」とは異なり、
市町村民税算出時に控除できる社会保険料控除や
生命保険料控除等も差し引いた後の金額となります。
それなりの税務知識がないと理解できないのが難点です・・・。
【ポイント2:保険料は、均等割と所得割の2つからなる】
保険料は、均等割と所得割の合計額となります。
●均等割
被保険者一人ひとりに均等に課せられる額です。
令和5年における千葉県の均等割額は43,400円ですが、
東京都は46,400円、神奈川は43,100円と微妙に異なります。
均等割額は、世帯の所得状況によって、2〜7割の
軽減措置があります。
後期高齢者医療制度加入日の前日に健康保険の被扶養者だった者は、
加入後2年を経過する月(≒77歳に到達する月の前月)分まで
5割に軽減される措置もあります。
●所得割
所得割額は、
賦課のもととなる所得金額×所得割率で算出されます。
令和5年における千葉県の所得割率は8.39%ですが、
東京都は9.49%、神奈川は8.78%とこれまた異なります。
特筆すべきことに、
後期高齢者医療制度加入日の前日に健康保険の被扶養者だった者は、
当分の間、所得割の負担が一切ありません!!!
【ポイント3:保険料の支払い方法は自分で選択できる】
後期高齢者医療制度の保険料は、
老齢年金から天引きされる「特別徴収」だけでなく、
口座振替(家族の口座でもOK)や納付書による「普通徴収」も含め、
自由に選択できます。
面白いことに、
介護保険ではこの選択の自由がありません。
介護保険の保険料は、
老齢年金額が年額18万円以上であり、
かつ後期高齢者医療制度の保険料との合計額が、
年金額の2分の1を超える場合を除いて、
強制的に特別徴収にされてしまいます。
後期高齢者医療と介護保険で取り扱いが異なる理由ですが、
後期高齢者医療制度の立法当時の野党の発言力が強く、
法案を成立させたい与党が譲歩した結果、
自由に選択できるようになったと聞いています。
【ポイント4:窓口負担割合は、課税所得により1〜3割】
窓口負担割合は、下記のルールにより判定されます。
・課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の現役並み所得者
⇒世帯全員が3割負担
・世帯内75歳以上の者等のうち課税所得が28万円以上の者がいる
⇒世帯の年金収入+その他の合計所得金額により、1〜2割
・世帯内75歳以上の者等のうち課税所得が28万円以上の者がいない
⇒世帯全員が1割負担
2割負担となる場合、令和7年9月30日までは、
1月間の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える
激変緩和措置があります。
【まとめ:医療に関する出費を減らすためにはどうすればよいか?】
保険料を下げるためには、
賦課のもととなる所得金額を減らす必要があるので・・・、
・事業所得で赤字を出す。
・給料を減らす(退職金は高額でもOK)。
・老齢年金でなく、遺族年金や障害年金を受給する。
等が考えられますが、手っ取り早い方法としては、
75歳の制度加入時に誰かの健康保険の被扶養者であれば
均等割、所得割とも相当程度低くなるでしょう。
窓口負担割合を下げるためには、
課税所得を減らす必要があるので・・・、
・小規模企業共済に加入する・掛金を増やす。
・家族の分の保険料も普通徴収で自分が負担する。
・家族の医療費を自分が負担する。
等が考えられますが、ふるさと納税は寄付金控除であり、
税額控除なのでNGです。
資産運用がブームのようですが、実務では、
株式等に係る譲渡所得や配当所得がある場合は、
・特定口座での申告不要制度を選択した場合
・総合課税を選択した場合
・申告分離課税を選択した場合
で課税所得等が変動するため、
税と社会保険を総合的に判断する必要があり、
最適解を見つけるのはある程度の知識と努力が必要でしょう。