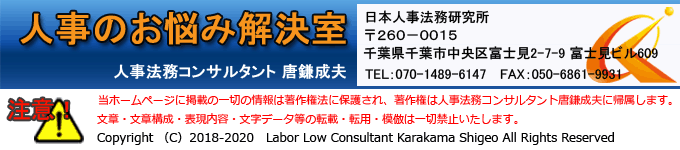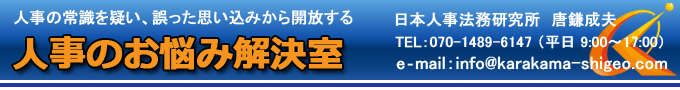
※2023年9月19日発行のメールマガジンの内容を反映し、大幅に加筆修正しています。
労働基準法には、
「休日は週に1回以上与えろよ。」と書かれています。
この週休制は、
法施行当時(昭和22年)からあるルールなのですが、
戦後のとても忙しい時代に、企業は本当に守れたのか?
と疑問ではあります。
労働基準法の生みの親である寺本廣作氏の著書
「労働基準法解説(昭和23年発行)」
に週休制を採用した経緯が記載されています。
これによれば、戦時中は、
月間休日2日制を採用する企業が全体の71%と圧倒的過半数
なのですが、戦後(昭和22年当時)は、
週休制を採用する企業が全体の38%まで増え、最多の休日制度
だったこともあり、週休制を採用したとのこと。
ただし、
36協定による法定休日出勤ルールも施行当時から存在したので、
実態としてどれだけの休日が与えられたのか?は不明ですが。
2023年4月から、
「月60時間超の時間外労働の割増率は、50%以上」
ルールが、中小企業にも適用されました。
また、2024年4月には、
時間外・休日労働の上限規制の適用が猶予されていた
建設業、トラック運送業、勤務医師にも適用が
開始されます。
これらの労働時間ルールにキッチリ対応するためには、
残業や休日出勤が、時間外労働に該当するのか?
それとも法定休日労働に該当するのか?
を明確に区別する必要があります。
今回は、
勤怠管理をする上で重要な論点である、
法定休日を特定すべきか?
について考えてみたいと思います。
※今回のテーマは、弁護士石嵜伸憲編著
「労働行政対応の法律実務【第2版】(中央経済社)」
を参考にさせていただきました
【法定休日の基礎知識】
法定休日は労働基準法第35条に規定されており、
・原則として、週1回(1日)。
・原則として、暦日(0時から24時まで)。
・法定休日は特定することが望ましい。
という簡単明瞭なルールとなっています。
週休2日制や祝日を休日とするなど、
週に2日以上の休日が存在する場合は、
法定休日以外の休日は、所定休日となります。
所定休日には、35条の規制が及びませんので、
所定休日は、
暦日である必要はなく、
連続24時間である必要もなく、
予め特定する必要もなく、
そもそも与える必要もありません。
【法定休日労働の規制は、かなり緩い。】
法定休日は、本来であれば、
会社が労働を命じることができない日なのですが、
以下の4項目を順守した場合、労働を命じることが
できちゃうというヘンテコな日なのです。
1.36協定にて、法定休日労働可能日数を協定し、
労働基準監督署に届け出ていること。
2.「法定休日労働させることがある。」旨を労働条件
として明示していること。
3.35%以上割増した賃金を支払うこと。
4.時間外労働時間+法定休日労働時間の合計時間は、
1月間で100時間未満、複数月平均で80時間以下
であること。
したがって、上記4.の範囲内でありさえすれば、
・法定休日労働の日数に法律上の上限は存在しない。
「法定休日労働は、1ヶ月間に5日まで」と協定した場合、
365日ぶっ通しで働いただけでは、違法とはならない。
・法定休日労働には、1日の労働時間の上限が適用されない。
法定休日労働は、「1日の労働時間は8時間まで。」という
法定労働時間の規制(第32条)の枠の外にあるので、
休憩時間1時間を除いて、1日23時間働いただけでは、
違法とはならない。
のように、現実的にはかなり緩い状況にあります。
【法定休日を「特定する」とはどういう意味か?】
労働基準法は、労働条件通知書や就業規則に
休日に関する事項を記載し、労働者に明示しなければならない
と規定しています。
「法定休日は1週間に1回与える。」のようにあいまいな
記載内容でも違法ではないのですが、労働者保護の観点からすれば、
「法定休日は日曜日とする。」のように具体的に特定の曜日や日付等を
休日と特定(指定)することが望ましいと行政は考えています。
つまり、巷で言う「法定休日の特定」とは、
労働条件通知書や就業規則に特定の曜日や日付等を
休日と指定(記載)することと言えます。
【法定休日の選択権は会社にある】
週休2日制や祝日を休日とするなど、
週に2日以上の休日が存在する場合は、
1日は法定休日、残りの休日は全て所定休日となります。
労働契約で「法定休日は日曜日とする」
と指定してあれば、日曜日が法定休日になりますが、
指定されていなければ、休日付与請求権は選択債権
であることから、債務者である会社にその選択権が
あります。
・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
民法406条
債権の目的が数個の給付の中から選択によって
定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
つまり、1週間に2日以上の休日がある場合で、
就業規則等で法定休日を予め特定していないときは、
会社がその都度、法定休日を任意に指定することが
可能ということになります。
もし、会社がこの選択権を行使しない場合には、
行政通達等により自動的に法定休日が決定される
ことになります。
【法定休日決定の3パターン】
<パターン1:あらかじめ特定>
「法定休日は、毎週日曜日とする。」のように、
法定休日をあらかじめ特定していた場合、
その週に所定休日が何日あろうとも、
日曜日に働けば、必ず法定休日労働となり、
休日労働の割増賃金(35%以上)を支払わなければ
なりません。
法定休日を特定した場合、
法定休日と所定休日の区別が非常に簡単なので、
知識不足の担当者でも給与計算が対応可能という
メリットが考えられます。
<パターン2:事前または事後に指定>
技巧的ではありますが、以下の方法が考えられます。
①就業規則上は法定休日を特定せず、当該週の前週の最終営業日までに会社が法定休日を指定できる「事前指定権」を定めておく
②当該週の翌週の初日に会社が事後的に法定休日を指定する「事後指定権」を定めておく
③就業規則で法定休日を日曜日などと特定した上で、法定休日と所定休日を振り替える「振替権」を定めておく
これであれば、
・36協定で定めた時間外労働と法定休日出勤
・月60時間超の時間外労働の割増率は、60%以上
・時間外労働と法定休日労働を合計して、1月間で100時間未満、複数月平均で80時間以下
等の労働時間ルールを考慮した上で、法定休日を
指定することが可能となります。
ただし、
それなりの知識のある者が担当しないと
ベストな選択肢が判断できない可能性があり、
注意が必要です。
<パターン3:行政通達等により自動的に法定>
就業規則等で法定休日をあらかじめ特定せず、
法定休日の選択権も行使しない場合には、
法定休日は、以下ルールにより事後に確定します。
・日曜日に休み、月曜日から土曜日まで働いた場合
⇒唯一の休日である日曜日が法定休日となる。
・完全週休二日制で日曜日と土曜日に休んだ場合
⇒最初に暦日の休日が確定した日曜日が法定休日となる。
・日曜日から土曜日まで1週間休日なしで働いた場合
⇒休日なしが確定する週最終日の土曜日が法定休日労働となる。
法定休日を特定した場合と比べ、労務管理や給与計算が
複雑・面倒くさくなる欠点があります。
法制定(昭和22年)から平成30年の働き方改革法まで、
実に70年もの長きに渡り、36協定届枚を出せば、
法定休日労働は、理論上何でもアリの無法地帯でした。
働き方改革法により、時間外労働と合計して、
1月間で100時間未満、複数月平均で80時間以下
という上限が初めて設けられましたが、
時間外労働の規制強化と比べると、随分と緩い気がします。
トップページへ戻る。