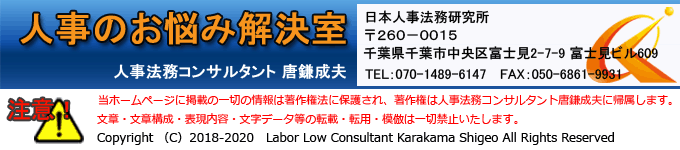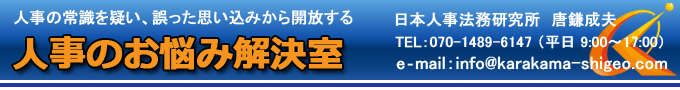
最終更新日:令和7年8月7日
子どもが保育圏に入園する際には、
無理なく新しい生活リズムに慣れるように、
徐々に在園時間を延ばして行くそうですが、
これを「慣らし保育」と呼ぶそうです。
<事例>
令和4年10月15日に出産した女性社員が
子が1歳になるまで育児休業を取得。
令和5年10月1日から保育園入所を希望したが、
満員で入園できず、やむなく育児休業を延長。
令和6年4月1日から保育園に通園できるようになったが、
4月中は慣らし保育のため、5月1日から職場復帰。
さて、この場合、
社会保険料の免除や育児休業給付金は
どのような取り扱いになるのでしょうか?
【育児休業には3種類ある】
育児介護休業法では、
以下の3つの育児に関する休業を定義しています。
(1)原則的な育児休業(育児介護休業法第2条)
原則として最長で1歳まで。
保育園に入園できない場合、最長2歳まで延長可能。
(2)所定労働時間の短縮措置を講じない場合(同法第23条)
3歳未満の子を養育する労働者に対し、
所定労働時間の短縮措置を講じない場合、
育児休業に関する制度に準ずる措置または
始業時刻変更等の措置を講じる義務あり。
(3)子が小学校に入学するまでの措置(同法第24条)
育児休業に関する制度等の措置を講じる努力義務あり。
(2)や(3)の「育児休業に関する制度に準ずる措置 」ですが、
厚生労働省が公表している「育児・介護休業法のあらまし」 によれば、
「法に基づく育児休業の制度と全く同じ制度である必要はありませんが、
本人の申出に基づくものであること及び男女が対象となることなど、
考え方は共通すべきものです。」
とされています。
以上を踏まえると事例の育児休業は、
以下の3つの期間に分けることができます。
第1期:原則的な育児休業
産休明け(令和4年12月11日)から1歳(令和5年10月13日)まで
第2期:保育園に入園できないため、延長で育児休業
1歳(令和5年10月14日)から入園(令和6年3月31日)まで
第3期:慣らし保育期間中の育児休業に準ずる措置による休業
入園 (令和6年4月1日)から職場復帰 (令和6年4月30日)まで
【社会保険料の免除】
社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は、
育児休業「等」の期間中、申し出れば免除されます。
育児休業「等」とは、育児介護休業法の
(1)の育児休業
(2)の育児休業に関する制度に準ずる措置による休業
(3)のうち、3歳未満の子を養育する労働者の育児休業に準ずる措置による休業
をいいます。
具体的な免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月と
その育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
その育児休業等を開始した日の属する月から
その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月まで
となります。
事例の場合、第1期および第2期は(1)に該当し、
第3期は(3)に該当するので、休業の全期間が免除対象となり、
育児休業等を開始した日=令和4年12月11日が属する月
⇒令和4年12月から
育児休業等が終了する日の翌日=令和6年5月1日が属する月の前月
⇒令和6年4月まで
社会保険料が免除されることになります。
【雇用保険の育児休業給付金】
育児休業給付金の支給対象となる育児休業は、条文上、
育児介護休業法の育児休業と全く関係ありませんが、
実質的には、ほぼ同じ定義になっています。
支給期間は、
(1)原則
1歳に満たない子を養育するための休業期間
(2)1歳に達する日後の期間について、保育園に入園できない場合
1歳6ヶ月に満たない子を養育するための休業期間
(3)1歳6ヶ月に達する日後の期間について、保育園に入園できない場合
2歳に満たない子を養育するための休業期間
となります。
事例の場合、
4月1日から30日までの慣らし保育に係る休業期間、
育児休業給付金は支給されないのでしょうか?
法令だけでなく、業務取扱要領まで調べたのですが、
慣らし保育に関する記述が見つけられなかったので、
ハローワークに照会した結果、以下の回答を得ました。
・慣らし保育は、支給期間延長の要件とはならない。
・ただし、すでに延長されている支給期間内に慣らし保育のため、
休業する場合、その休業期間は支給対象となる。
事例であれば、慣らし保育を理由に
1歳6ヶ月に達した4月14日以降の期間延長はしないが、
すでに期間延長されている4月13日までについては、
慣らし保育のために休業するのであれば給付金は支給される
ことになります。
ちなみに、育児休業期間中に
例外的・一時的・臨時的に就労する場合、
就業日数が月10日(10日を超える場合は80時間)以下
であれば、育児休業していることを否定されることはなく、
社会保険料は免除されますし、給付金も支給されます。