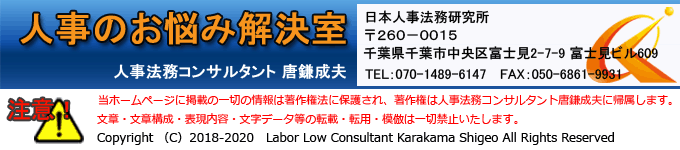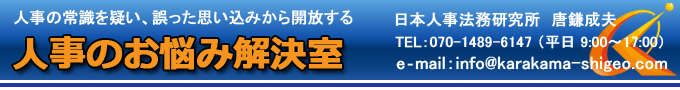
最終更新日:令和7年8月4日
建設現場の職人や交通誘導員等のガテン系(死語?)
の仕事に女性が就くことも珍しくなくなりました。
一昔前まで、
ガテン系企業は、ほぼ100%男性で占められていましたが、
人手不足や性別による職業の垣根がなくなったこと等により、
現代では、ガテン系企業にも女性が進出しています。
ガテン系の人事担当者(特に男性の場合)は、
「女性作業員から妊娠したという報告があったのだが、
今まで全く経験がなく、どう対応したらよいのかわからない!」
という悩みを持つことが考えられます。
ここでは、
社員が妊娠したら、人事担当者はどう対応すればよいか?
について考えてみたいと思います。
【会社の社会保険は結構手厚い】
労働者が加入する社会保険は、
・会社の社会保険≒健康保険+厚生年金保険
・市町村の社会保険≒国民健康保険+国民年金
の2パターンがあります(一部例外あり)。
会社の社会保険には、
以下の給付金制度がありますが、
市町村の社会保険にはありません。
・出産手当金:産前産後期に休暇を取得すると支給
・傷病手当金:産前産後期以外に体調不良で欠勤すると支給
・育児休業給付金:原則1歳、最長で2歳まで支給
会社の社会保険の保険料は、
産前産後および育児休業期間中は免除されますが、
市町村の社会保険は以下のとおり、
産前産後休暇期間中に限り免除されます。
<産前産後休暇期間>
・国民年金保険料免除:平成31年4月から実施
・国民健康保険料免除:令和6年1月から実施
<育児休業期間>
・国民年金保険料免除:令和8年10月から実施予定
・国民健康保険料免除:当面なし。
以上を踏まえると、
会社の社会保険と市町村の社会保険を比較すると、
会社の社会保険の方が出産・育児に手厚い制度
になっています。
会社の社会保険に加入している場合、
「妊娠・出産するので退職します。」はもったいない
と言えそうです。
ちなみに、
健康保険には任意継続被保険者という制度がありますが、
任意継続被保険者の場合、保険料は一切免除されません。
【妊娠・出産等を理由とした不利益取り扱いは禁止】
妊娠や出産等を理由として、解雇をしたり、
降給や降格等の労働条件の不利益変更をしたりする
ことは、雇用機会均等法により禁じられています。
特に、
産前産後休業期間+その後30日間は、
労働基準法により解雇が絶対禁止されています。
なお、雇用機会均等法には、
他社からセクハラ防止措置について協力を求められた
場合、これに応じる努力義務が規定されていますが、
マタハラについては同様の義務が規定されていません。
【妊娠中の働き方は、本人の意思を考慮して決定する】
雇用機会均等法13条は、
妊産婦に対して通勤緩和等の必要な措置を取る
義務を会社に課しています。
妊娠した社員に措置を求める意思がある場合、
会社は「母性健康管理指導事項連絡カード(以下、カードと略)」
や担当医師の診断書の提示を求め、その内容を考慮して、
業務の変更等の必要な措置を取ることになります。
ただし、社員の要望事項が、
通勤緩和または休憩に関する措置であるときは、
会社はカードや診断書の提示がなくても相応の対応を図る
必要があります。
雇用機会均等法13条の措置義務は、
「社員本人から申し出がある」ことが前提条件のため、
社員に会社に措置を求める申し出をする意思がない場合、
会社は措置を取る義務が発生しないことになります。
本人に措置を求める意思がなければ、
本人には有料のカードを作成する意味がなく、
会社は措置を取る義務が発生していない以上、
妊娠した社員の体調等を客観的に確認したくても、
カードの提示を求めることはできません。
会社が、
社員の妊娠を理由として行き過ぎた措置を行った場合、
不利益取り扱いになってしまう恐れがあります。
安全や健康面で特に問題がなく、
社員と面談して、本人に措置を求める意思もなければ、
妊娠中も従来の業務を担当してもらうことになるでしょう。
妊娠は病気ではありませんが、
ひどいつわりは妊娠悪阻(おそ)という病気になります。
社員が体調不良で欠勤が続いた場合は、病気を疑う必要があるので、
会社は診断書やカードの提出を求めて、社員の体調を客観的に確認し、
安全・健康配慮義務に則り、必要な措置を取るべきです。
【出産が近づいたら、出産後の意向を確認する】
育児介護休業法には、
社員から妊娠・出産の申し出があった場合、
会社は以下の事項を当人に周知(≒説明)し、
出産後の意向を確認をする義務が規定されています。
① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
② 育児休業・産後パパ育休の申出先
③ 雇用保険の育児休業給付金に関すること
④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い
この周知・意向確認義務は、
配偶者が出産する旨の申し出があった男性社員も対象
になるので注意しましょう。