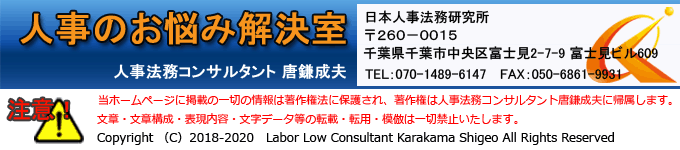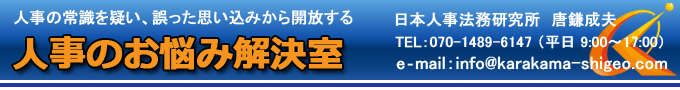
最終更新日:令和7年8月10日
中小企業の社長や長年に渡り採用を担当した者であっても、
採用時に当人の技術・経験に見合う適正な給与額を設定することはなかなか難しく、
デキる社員の給与を低めに設定した結果、すぐに転職されてしまったり、
デキない社員の給与をウッカリ高めに設定した結果、激しく後悔したり、
ということはよくある話です。
とある中小企業の社長と新入社員である田中氏との間で、
「田中氏の技術・経験を考慮すると
月30万円の給与はちょっと低いかもしれない。
そこで、入社後半年間の働きぶりによっては、
採用時にさかのぼって昇給することもやぶさかでないから、
ぜひ頑張っていただきたい!」
というような約束(契約)をしたとします。
田中氏は技術・経験を活かして頑張って働いたので、
社長の想定を遥かに超える結果を残しました。
社長と田中氏は改めて話し合い、入社時の約束通り、
採用時にさかのぼって5万円昇給することで合意しました。
半年間の昇給差額分の30万円(5万円×6ケ月)は、
一括で支給することになりました。
さて、この場合、
労務管理上どのように事務処理すべきでしょうか?
<さかのぼり昇給とは?>
多くの大企業では新年度となる4月に向けて、
労働組合と経営者が労働条件について交渉する
いわゆる「春闘」が行われていますよね。
重要な交渉事項の1つに昇給がありますが、
昇給についての交渉が難航した場合、
夏頃にやっと合意に至ることがあります。
たとえば、
4月に遡及して昇給することが8月に決定した場合、
4〜7月にすでに支払われている旧賃金との昇給差額分
をまとめて8月に支払うことがあり、これを「さかのぼり昇給」
などと呼びます。
春闘がない中小企業でも、
冒頭のようなさかのぼり昇給事例はあり得る話でしょう。
ちなみに、さかのぼり「降給」については、
「具体的に発生した賃金請求権を
事後に締結された労働協約や
事後に変更された就業規則の遡及適用により
処分又は変更することは許されない」
(平成八年三月二六日最高裁判例民集五0巻四号千八頁)
という最高裁判例があるとおり、原則として許されません。
<労働基準法・労災保険法>
労働基準法に規定されている
解雇予告手当や休業手当は、
平均賃金を基に算出されます。
平均賃金は、
事由発生日前3ヶ月間の賃金総額から算出されますが、
算定対象期間中にさかのぼり昇給があった場合、
どうするのでしょうか?
・事由発生後に遡ってベースアップされた場合の基礎賃金(昭和23年8月11日 基収第2934号)
・新旧賃金の差額の取り扱い(昭和22年11月5日 基発第233号)
という関連通達があり、これを要約すると以下のとおり。
・事由発生時において昇給額が確定している場合
⇒追加(=昇給)差額分は各月に支払われたものとして平均賃金を計算する。
・事由発生時において昇給額が確定していない場合
⇒労働者が現実に受けまたは受けることが確定した賃金の範囲内すなわち昇給差額分は考慮せずに平均賃金を計算する。
ちなみに、
上記通達には以下の趣旨の記載もあり、参考になります。
・賃金台帳の記載に当たっては、実際の支払い月の該当欄に遡及支払い分であることを明記して記入する。
・追加額(=差額の一括支給分)は、平均賃金の算定対象外である「臨時に支払われた賃金」ではない。
労災保険の各種給付の算定基礎となる「給付基礎日額」は、
原則として、平均賃金に相当する額とされており、
上記の労働基準法の取り扱いに倣えばOKでしょう。
<雇用保険法>
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、
退職直前の6ヶ月間に支払われた賃金を基礎に算出される
「賃金日額」に基づき支給されます。
雇用保険の実務マニュアルである
「雇用保険業務取扱要領」によれば、
賃金日額算出時におけるさかのぼり昇給の取り扱いは
以下のとおりとなります。
・離職前までさかのぼって昇給が行われることが離職後に決定した場合のその追加分は賃金日額の算定の基礎に算入されない(50503ハ)。
・さかのぼって昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後に支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、その計算の結果が離職時までにまだ算出されていない場合にも、事業主としては支払い義務が確定したものとなることから、賃金日額の算定の基礎に算入する(50501ト)。
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎても
なお支払われないものを「未払賃金」などと呼びますが、
未払賃金の取り扱いはさかのぼり昇給とはまったく異なり、
以下となります。
・未払額の認定に当たっては、当該労働者の稼働実績、過去の賃金額等に基づいて確実と認められるもののみを認定し、事業主又は労働者が未払賃金であると称する場合であってもその算定基礎の明確でないものは、未払額として認定しない(50609)。
雇用保険には、
定年退職後の賃金減少を補う給付金として
「高年齢雇用継続給付」もあります。
高年齢雇用継続給付は、
雇用月に実際に支払われた賃金に応じて支給されますが、
さかのぼり昇給の取り扱いは雇用保険業務取扱要領によれば、
以下のとおりです(59142)。
・雇用月に実際に支払われた賃金とは、当該雇用月に支払われた賃金のみをいい、当該雇用月を対象とした賃金であっても、他の月に支払われた賃金は、当該雇用月の賃金として算定しない。
・労働協約等の改定に伴い賃金が遡って引き上げられ、過去の雇用月に係る差額分が支払われた場合、これら差額分を遡って過去の雇用月に再配分せず、当該支給された月に支払った賃金として取り扱う(したがって、当該差額支給があった月が雇用月である場合には、当該差額はその雇用月に支払われた賃金として取り扱う)。
・未払賃金がある場合は、当該未払額を含めて算定する。この未払額とは、支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎても、なお、支払われないものをいう。
<労働保険徴収法>
ハローワークが無料で配布している
「雇用保険事務手続きの手引き」や
労働保険料申告書と一緒に郵送される
「労働保険年度更新 申告書の書き方」に
よれば、以下のとおり。
・遡って昇給した賃金は労働保険料の算定基礎になる。
・離職後に決定された給与(昇給含む)及び賞与は労働保険料の算定基礎にならない。
・離職後支払われた場合で在職中に支払いが確定した昇給差額は労働保険料の算定基礎になる。
労災保険および雇用保険の取り扱いを考慮すると、
当然の措置と考えられます。
<健康保険法・厚生年金保険法>
狭義の社会保険における標準報酬月額は、
定時決定=4,5,6月の給与で決めるいわゆる「算定」と、
随時改定=固定的賃金変動後の給与で決めるいわゆる「月変」により、
決定されます。
さかのぼり昇給・降給については、
・健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて(昭和36年1月26日 保発第四号)
という通達や
「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」等にて、
以下のとおり言及されており、
特例的な算出方法(保険者算定という。)によります。
●定時決定
・3月以前にさかのぼった昇給の差額分または3月以前の給与を4、5、6月のいずれかの月に受けた場合
⇒3月以前の昇給差額分(または遅配分)を除いた報酬月額の総計から報酬月額を算出する。
・4、5、6月のいずれかの月の給与が7月以降に支払われる場合(給料の遅配)
⇒7月以降に支払われる月以外の月を対象月として報酬月額を算出する。
●随時改定
・昇給及び降給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合
⇒随時改定されるべき月以降において受けるべき報酬月額により算出する。
要するに、差額支給・減額分は考慮せずに報酬月額を算出するということ。
起算月は、昇・降給後の報酬が初めて支払われた月とする。
・給与計算のミス等により、本来の支給月に正しい報酬を支払うことができず、翌月以降に差額調整を行った場合
⇒単なる給与の支給誤りであれば、本来の昇・降給月を起算月として随時改定を行う。
労働保険と異なり、
社会保険ではさかのぼり「降給」も想定されています。
その理由は、
労働保険の被保険者は労働者限定であるのに対し、
社会保険では役員も被保険者になり得るからです。
労働法令の保護を受けない役員の場合、
取締役会と株主総会の意思決定を経れば、
合法的にさかのぼり降給ができてしまいますので。