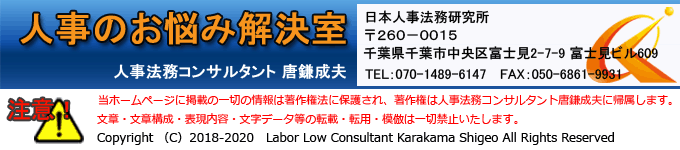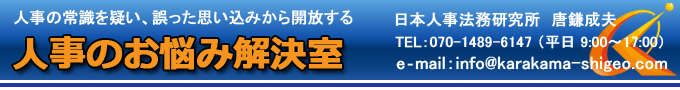
最終更新日:令和7年8月10日
賞与額は、具体的な金額ではなく、「月給の○ヶ月分」
と表示されることも多いのですが、最近ふと、
「基本給と賞与の最適比率を合理的に算出できないか?」
と考え、労働法や社会保険法を再確認してみました。
ここでは、
社会保険制度も踏まえた基本給と賞与の最適比率
について検討した結果をシェアしたいと思います。
賞与って、いったい何だい?
社会保険と賞与についての基礎知識
ステージ別、基本給と賞与の最適比率
労働基準法上、
賞与に関する定義は具体的に示されていませんが、
行政通達において、以下のとおり規定されています。
「賞与とは、定期または臨時に、原則として
労働者の勤務実績に応じて支給されるものであって、
その支給額が予め確定されていないものをいうこと。
定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、
名称の如何にかかわらず、これを賞与とみなさないこと。」
賃金は、
毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければ
なりませんが、賞与にはこのルールは適用されません。
この他にも、賞与は賃金とは異なり、
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与は
最低賃金や割増賃金の算定基礎に含まれませんし、
3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与は、
平均賃金の算定基礎にも含まれません。
狭義の社会保険(健康保険と厚生年金保険)では、
「『賞与』とは、いかなる名称であるかを問わず、
労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、
三月を超える期間ごとに受けるもの」
と定義しており、
定期的に支給されかつその支給額が確定していても
賞与として取り扱って問題ありません。
実務では行政通達において、
以下のいずれかに該当する場合は、
賞与ではなく報酬として取り扱うことになっています。
・賞与の支給が諸規定によって年間を通じ4回以上の
支給につき客観的に定められている。
・賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上
行われているとき。
広義の社会保険各法において、
賞与はどのような取り扱いを受けるか?
確認してみましょう。
話を単純化するため、以下では、
・基本給以外の諸手当等は考慮せず、基本給額=月給額。
・賞与は夏季と冬季の年2回支給。
とします。
●労災保険
業務上災害によって、療養のために仕事を休んだり、
治ったけど障害が残ったり、死亡したりした場合、
給付基礎日額(≒平均賃金)に基づき各種の保険給付
が支給されます。
労災保険では、
保険給付の他に、社会復帰促進事業として
各種の特別支給金が支給されます。
特別支給金には、
定額制のものと給与比例制のものの2種類がありますが、
給与比例制の特別支給金は、休業特別支給金を除き、
3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金-≒賞与の
過去1年分である「算定基礎年額」に基づき支給されます。
●雇用保険
雇用保険の主たる保険給付として、
基本手当(いわゆる失業手当)がありますが、
基本手当の日額は、賃金日額の45〜80%
となります。
賃金日額には、
3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金は含まれないので、
年2回支給される賞与は、賃金日額の対象外となります。
基本手当の他にも
・育児休業給付
・介護休業給付
・高年齢雇用継続給付
等の保険給付がありますが、賞与は支給額に影響しません。
賞与についても雇用保険料はキッチリ徴収されますが、
保険給付には一切繋がらない(払い損?)と言えます。
●健康保険
私傷病で仕事を休んだ場合、健康保険から
標準報酬月額に応じて傷病手当金という
保険給付が支給されます。
高額な医療行為を受けたときに支給される保険給として、
高額額療養費がありますが、その際の自己負担額も、
標準報酬月額に応じた金額に設定されています。
標準報酬月額≒月給額であり、賞与額は影響しません。
千円未満の端数を切り捨てた標準賞与額に対して
健康保険料が徴収されますが、
保険給付には一切繋がらない(払い損?)と言えます。
●厚生年金保険
厚生年金も標準賞与額に対して厚生年金保険料が徴収
されますが、老齢年金等の保険給付の際に反映されます。
社会保険制度を考慮した基本給と賞与の最適比率について、
以下のステージに分けて、検討してみます。
ステージ1:最低賃金〜世間相場
ステージ2:世間相場〜月給27万円
ステージ3:月給27〜51万円
ステージ4:月給51〜63万円
ステージ5:月給63〜81万円
ステージ6:月給81万円以上
ステージ1の場合、賞与は支払うべきでなく、
給与の全額を基本給(≒賃金)として支払うべきです。
理由その1:賃金は最低賃金以上である必要がある
賞与は最低賃金を判定する際、計算基礎に含まれません。
所定労働時間が1日8時間で、週休二日制+祝日休みだと
月平均所定労働時間は163時間、最低賃金を1,100円と仮定すると、
基本給は最低でも月給18万円くらい必要になるます。
18万円程度の月給を支払えない会社は、
そもそも社員を雇うことができないことなります。
理由その2:世間相場以下の基本給では求人が困難である
基本給は、求職者が必ず確認する労働条件の1つです。
基本給が世間相場以下の場合、
他の労働条件を確認するまでもなく、
多くの応募者が離れていくことが予想されます。
一流職人がいる名店やカリスマ経営者の会社等、
求人力があり、給与が選択要素とならない例外を除き、
世間相場を超える基本給を払えるようになるまでは、
賞与は支給すべきでないと考えます。
理由その3:賞与のない会社は3割くらいある
職業紹介大手のインディードの記事によれば、
厚生労働省が公表している令和4年の
「毎月勤労統計調査」の結果によると、
ボーナスがない会社の割合は約3割
だそうです。
とすれば、
求職者に選ばれる基本給を払えるようになるまでは、
賞与が支給できないことに悩むヒマがあったら、
企業業績向上に注力すべきでしょう。
世間相場を超える基本給となるステージ2の場合、
1回当たりの賞与額は、労災保険の特別支給金を
考慮すると、基本給の1.2ヶ月分が理想的です。
理由その1:労災の特別支給金が最大になる
労働・通勤災害の原因が第三者の行為による場合、
労災保険の保険給付は民事損害賠償と支給調整
が行われます。
相手方との示談が真正に成立しており、
示談金以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、
労災保険の保険給付は一切行われませんが、
特別支給金は支給調整されず、支給されます。
社員がウッカリした内容で示談してしまうリスクを考慮すると、
特別支給金は最大限受給できるようにしておくとよいでしょう。
変動制の特別支給金の日額である「算定基礎日額」は、
「算定基礎年額」を365日で割った金額です。
「算定基礎年額」は、
災害発生日前1年間に支払われた特別給与の総額
=直近の年2回の賞与の合計額となりますが、
・給付基礎日額×365日×20%相当額
・150万円
のうちいずれか低い額が上限となります。
以上を逆算していくと、
150万円≧年間賞与額≧(月給額÷30日)×365日×20%=月給額×2.43
のときに算定基礎日額が最大値となることになります。
したがって、
経済合理的な1回当たりの賞与額=基本給の約1.2ヶ月分
ということになります。
理由その2:賞与=基本給の1.2ヶ月分は世間相場並み
厚生労働省の「令和4年年末賞与の支給状況 」
によれば、令和元年末の賞与支給実績(平均)は、
従業員数毎に以下のとおりとされています。
・500人以上 :月給の1.49ヶ月分
・100〜499人:月給の1.24ヶ月分
・30〜99人 :月給の1.15ヶ月分
・5〜29人 :月給の1.01ヶ月分
企業規模だけでなく業種特性の要素もありますが、
賞与額が基本給の1.2ヶ月分という数値は、
世間相場並みと言えそうですね。
月給額が27万円以上となり、
標準報酬月額が28万円等級以上となると、
健康保険の高額療養費の自己負担額が増えます。
また、
70歳〜74歳の健康保険の被保険者は原則として、
かかった医療費の2割を自己負担しますが、
標準報酬月額が28万円等級以上の場合、
現役並み所得者と扱われ3割負担となります。
したがって、社員の私生活に配慮するならば、
月給額を27万円以上になるよう基本給を昇給させたい場合でも、
しばらくは基本給を27万円以上に昇給させず、
その代わりに賞与の支給率を上げるようにすれば、
賞与が増えても標準報酬月額の等級は変動しないため、
健康保険の自己負担増加を先延ばしできます。
月給額が515,000円以上となり、
標準報酬月額が53万円等級以上となると、
健康保険の高額療養費の自己負担額が
次の段階に進み増額されます。
また、
雇用保険の賃金日額は、
離職日の年齢に応じて上限額が設定されており、
「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減に応じて
毎年8月1日に変更されます。
離職時に45歳以上60歳未満の場合に上限額が最大値となり、
令和7年8月現在、17,740円ですが、
これを月給に逆算すると、53万円くらいになります。
つまり、月給が53万円以上に昇給しても
失業手当受給の際にうま味がないことになります。
したがって、ステージ3の時と同様に
月給額を50万円以上になるよう基本給を昇給させたい場合、
しばらくは基本給を50万円以上に昇給させず、
その代わりに賞与の支給率を上げるようにすれば、
健康保険の高額療養費の自己負担増加を先延ばしできます。
月給額635,000円以上に昇給すると、
標準報酬月額は厚生年金の最高等級である
65万円等級になります。
これ以降、いくら基本給を昇給しても、
厚生年金の等級は変わらないので、
厚生年金保険料は増えることがなく、
将来貰える年金額も増えません。
健康保険は月給1,355,000円以上の場合、
標準報酬月額は最高等級1,390,000円になるので、
基本給を635,000円以上に昇給しても、
1,355,000円までは傷病手当金は増えていきます。
以上を考慮すると、このステージでは、
賞与の支給率を上げるよりも基本給を昇給した方が、
厚生年金保険料は増えず、傷病手当金は増える
ことになります。
このステージに該当する者は上級職位が予想され、
下級職と比べて成果に連動する賃金≒賞与との親和性が
高いと思われます。
月給81万円以上に昇給すると、
健康保険の標準報酬月額が83万円等級以上となり、
高額療養費の自己負担額が最高段階に進み増額されます。
以上を考慮すると、基本給は899,999円を上限とし、
基本給の昇給想定分を含めて、賞与の支給率を決定
するとよいでしょう。
実務では、
基本給や賞与を決定する際に最重要視すべきは、
会社の資金繰りであり社会保険ではありませんが、
社会保険の仕組みも一要素として考慮してあげると
ちょっとした配慮で社員の生活が楽になるかもしれません。