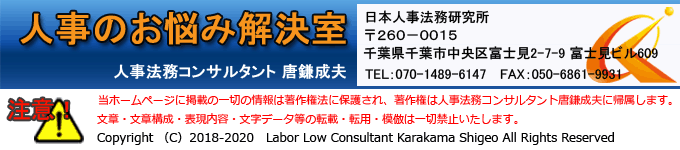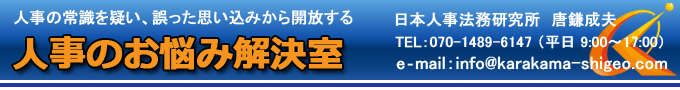
最終更新日:令和7年8月10日
台風接近時に計画休業した場合、
会社は休業手当を支払うべきなのでしょうか?
<A社の事例>
・社員数300人規模の企業であり、複数の事業を展開している。
・一部の社員は会社が運行している通勤バスを利用している。
・通勤バスのドライバーは社員である。
・台風が上陸する恐れがあり、電車等では計画運休が行われそうな状況。
・台風が接近している段階で被害予防措置としての休業(計画休業)を社員に命じた場合、休業手当の支払は必要か?
【そもそも、休業手当って何だい?】
社員が二日酔いが理由で欠勤した場合のように、
社員側の事情による不就労については、会社に
給料の支払い義務は当然ですがありません。
このような考え方を労働法の世界では、
「ノーワークノーペイの原則」と言います。
ノーワークノーペイの原則は、
社員から労務の提供を受けなかったときは、
会社は社員に給料を支払う義務はない。
という程度の意味を持ちます。
それでは、
社長が二日酔いのため会社が臨時休業になった場合
はどうなるでしょうか?
会社側の事情による不就労の場合にも、
ノーワークノーペイの原則が適用されてしまうと、
お給料で生活している社員はとっても困って
しまいます。
そこで、
労働者の味方である労働基準法では、
労働基準法第26条(休業手当)
使用者(≒会社)の責に帰すべき事由による休業の
場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければ
ならない。
と規定し、
一定額以上の給料の支払いを会社に強制しています。
この「平均賃金の60%以上の手当」のことを、
「休業手当」と言います。
月給制で残業代がない人の場合、平均賃金の60%は、
1出勤日あたりの賃金の約4割弱程度になるので、
思ったほど高額にはなりません。
【台風と東北大震災時の計画停電は似ていると思いませんか?】
「使用者の責に帰すべき事由」について、
いろいろな行政通達が出ているのですが、
台風に関するものは発出されていません。
ですが、東北大震災時に
「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」
という厚生労働省の通達が発出されていることに気が付きました。
台風と計画停電は、地震や雷等と異なり、
これから(未来に向けて)発生が予測される・し得る事象
という意味では、同じ性質を持つと思いませんか?
この通達に以下の記述があります。
3 計画停電が予定されていたため休業としたが、
実際には計画停電が実施されなかった場合については、
計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、
上記1及び2に基づき判断すること。
これを台風に読み替えると、
「台風の上陸が予測されたため休業としたが、
実際には台風が上陸せず被害がなかった場合については、・・・」
となろうかと思います。
「計画停電は上記通達があるから、
計画休業を指示した時でも場合によっては休業手当は支払い不要だが、
台風等の天災地変には直接的な通達がないから、
計画休業を指示した時は絶対休業手当を支払え!」
と労働基準監督官が指導してくる可能性がありますが、
その指導は論理的におかしいと考えます。
【事例検証】
昨今、台風による被害が予想される場合、
公共交通機関が計画運休を行うようになりました。
公共交通機関が計画運休するような事態発生時に、
それでも社員ドライバーに自社バスを運行させて、
他の社員の通勤手段を確保する道義的責任が会社にあるとは
私には思えません。
社員ドライバーに対しては、
会社は安全配慮義務を尽くす必要がありますし、
乗車した社員の安全を確保する必要もあります。
したがって、
公共交通機関(JRなど)が計画運休を正式決定。
⇒社員ドライバーの安全を考慮して、自社バスの計画運休を決定。
⇒バス通勤の社員は出勤が不可能となるため、計画休業を決定。
⇒使用者の責に帰すべき事由による休業ではないので、休業手当の支払いなし。
は十分あり得る判断だと考えます。
一方で、
自力で通勤が完結しており、
台風が逸れれば安全に出勤でき、普通に業務が可能な社員に対し、
「隣の部署が計画休業だから。」という理由だけで
自力通勤者にも計画休業を指示するのは、
使用者の責に帰すべき事由による休業として
休業手当を支払うべきでしょう。
ただし、こちらも、
「電力不足に伴う労働基準法の運用について」
という労働省(当時)の下記通達(上記通達の後段に記載あり。)
が発出されており、
事情によっては、休業手当の支払は不要だと考えます。
「・・・なお、休電があっても、
必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門
例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで
作業を休止することはこの限りでないのであるが、
現場が休業することによつて、
事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが
企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に
事務労働部門について作業を休止せしめた場合
休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。」
最後に、就業規則等において、
民法536条2項の適用を排除していない場合で、
会社が休業手当の支払い義務を認めてしまったときは、
社員から100%の賃金の支払いを求められる恐れがあるので、
休業手当の支払いは、ことさら慎重に判断しましょう。