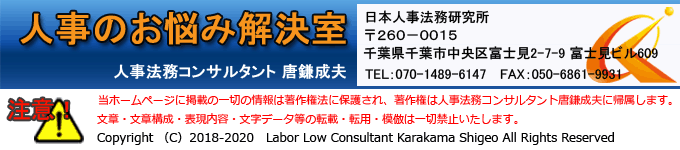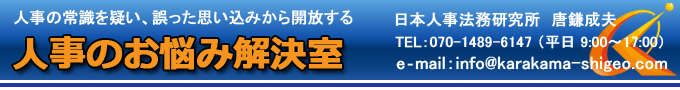
最終更新日:令和7年8月4日
令和6年4月以降、
労働契約を締結する際の労働条件明示ルールが変わりましたが、
対応状況はいかがでしょうか?
厚生労働省が公表しているQ&Aに、
「令和6年4月1日を契約の開始日とする契約の締結を3月以前に行う場合、新たな明示ルールに基づく労働条件明示が必要か。」
という設問に対し、
「契約の始期が令和6年4月1日以降であっても、令和6年3月以前に契約の締結を行う場合には、改正前のルールが適用され、新たな明示ルールに基づく明示は不要である。」
という回答があります。
有期雇用契約の期間は、半年契約や1年契約が多く、
4月1日を始期にしていることが多いと予想しますが、
1年契約の場合、
令和6年3月31日までに4月1日以降の労働契約を締結すれば、
新ルールは、令和7年4月1日以降の労働契約から適用となります。
うっかり、
新ルールに対応できていない人事担当者のために、、
新ルールに基づいた労働条件の明示はどうあるべきか?
について考えてみたいと思います。
【就業場所および業務の変更の範囲】
長期間、企業を経営していれば、
新しい事業所が出来たり、新しい事業を開始したり
労働契約締結時には想定し得ない人事異動が起こり得る
ものです。
無期雇用者(一般的には正社員)については、
定年まで何十年間にも渡り雇用を維持する必要があることから、
法的に(就業規則や労働契約書に明文の規定がなくても)
会社は強い人事権を持つとされています。
したがって、無期雇用者の場合は、
企業の将来の変化にも柔軟に対応できるように
就業場所および業務の変更の範囲は広めに記載すべき
です。
一方、有期雇用者については、無期雇用者と比べ
・業務内容が限定的・専門的であることが多い。
・契約期間が短期なので、その分だけ会社の人事命令権が弱い。
・変更があり得る旨を記載すると配置転換の期待感が生じる。
ということを考慮すると、
契約締結時に現実的に変更が予想される範囲内で限定的に記載すべき
と考えます。
たとえば、
専門職に就き給与水準が高い有期雇用者の
業務の変更の範囲を広く設定してあった場合、
突発的要因で担当業務がなくなってしてしまったとき、
「給与はそのままで、他の業務に配置転換してくれるよね?」
という期待感を持たれ、トラブルになり兼ねません。
「契約期間中、就業場所や業務に変更なし」
と記載していたとしても、
実際に就業場所や業務を変更する必要性が生じた場合は、
新しい労働条件について話し合って、
新しい労働契約を締結すれば事足ります。
結論として、
無期雇用の正社員は、変更の範囲を広く、
有期雇用の非正規社員は、変更の範囲を狭く
してはいかがでしょうか?
【有期契約の更新回数の上限】
従来から有期契約の更新上限を設定しており、
代替要員の確保も容易である(≒採用力がある)企業を除いては、
新たに更新上限を設定するのは如何なものか?と考えます。
労働契約法第18条によれば、
通算契約期間が5年間を超える有期雇用者が、
期間の定めのない労働契約を申し込んだ(希望した)場合、
会社は当該申込みを承諾したものとみなされます。
これを巷では、「無期転換ルール」などと呼んでいます。
有期契約の更新回数に上限を設ける理由は、
無期の労働契約を申し込む権利が発生しないようにするため
が一般的でしょう。
ですが、
・替わりの有期雇用者を新たに採用するのは、人手不足を考慮すると困難と考えられること。
・新たに更新回数に上限を設けた場合、その理由を説明する必要があること。
・無期雇用になったとしても、正社員にしなければならない訳ではないこと。
を考慮すると、今さら上限を設定しない方がよいのでは?
と考えます。
【無期転換申し込み機会および転換後の労働条件】
「無期転換後の労働条件は、希望者が出てきたら考えればいいや。」
は今後通用しなくなるので、会社としての運用方針を確定した上で、
書面にて明示する必要があります。
最も簡単なのは、たった一文
「無期転換後の労働条件は有期雇用時と同じ。」と記載する方法ですが、
以下の問題があると考えられ、まったく賛成できません。
・短期間の有期雇用と長期間の無期雇用を同じ労務管理下で運用するのには、無理がある。
・「契約期間中、就業場所や業務に変更なし」としてあった場合、無期転換後も人事権を行使できず、変更する場合は同意を得なければならない。
・正社員になるわけではないことを明示すべき。
定年退職者については、
労働局に「第二種計画認定」を申請し、許可を受けると、
無期転換を申し込む権利が発生しないという特例も考慮しつつ、
転換後の労働条件を決定するとよいでしょう。