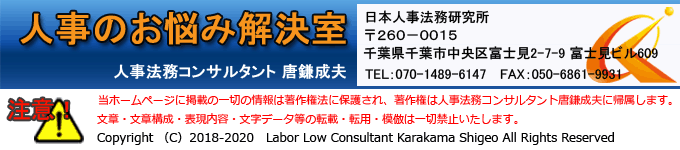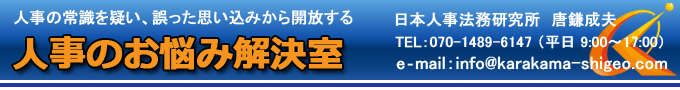
最終更新日:令和7年11月2日
カラカマは労務管理上、
通勤手当と出張旅費では大きな違いがあると考えており、
ことある毎にず〜っと(たぶん10年以上)妄想を続けてきたのですが、
ようやく自分なりの答えにたどり着きました。
ここでは、
通勤手当と出張旅費のさかいめについて、
カラカマが到達した結論についてお伝えします。
<通勤手当と出張旅費の基礎知識>
●通勤手当
・労働基準法の「賃金」に該当する。
・労働保険および社会保険法上の「賃金・報酬」に該当し、保険料算定の基礎に含まれる。
・経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額であれば、所得税は非課税。
●出張旅費
・実費弁償であれば、労働基準法の「賃金」に該当しない。
・労働保険および社会保険法上の「賃金・報酬」にも該当せず、保険料算定対象外。
・その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内であれば、所得税は非課税。
民法第484条および第485条に、
「別段の意思表示がないときは、
債務の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならず、
その費用は、債務者の負担とする。(持参債務)」とあるので、
労働者が労務の提供をするために会社に行く交通費は、
民事上は労働者が負担するのが原則と考えられます。
ただし、同法第485条後段に、
「債権者が住所の移転その他の行為によって
弁済の費用を増加させたときは、
その増加額は、債権者の負担とする。」とあるので、
入社後に会社の都合で勤務場所が変更になった結果、
交通費が増えてしまったときはその差額は会社が負担すべき
ということになります。
<通勤手当と出張旅費のさかいめ事例>
たとえば、
建設業における現場に行くパターンとしては、
1.「会社に出勤してから現場に行く」パターン
と、
2.「その者の住居から直接現場に行く」パターン
の2つが主として考えられます。
1.の場合、
A:社用車であろうと
B:公共交通機関であろうと、
その交通手段にかかわらず、「出張」に該当すると考えられるので、
通勤手当かな?と悩むことはまずなさそうです。
2.の場合、
民法第485条の「債権者が弁済の費用を増加させたとき」
に該当すると考えられるので、
その費用は、会社が負担すべきでしょうが、
通勤手当扱いとするべきか?出張旅費扱いとするべきか?
は不明です。
2.A:社用車貸与であれば出張旅費扱いだが、
2.B:公共交通機関利用の場合は通勤手当扱いという考え方は、
公平性が担保できていないので不合理だと思うのです。
また、
その時間的条件(1日、1週間、1月間、
半年間、日帰りか?宿泊を伴うか?)や
距離的条件(〇km、県内、同一地域内、国内)で
「通勤」と「出張」を分けるのも不合理だと思います。
2.はすべて通勤手当として取り扱うとした場合、
会社の都合で長距離(≒高額な交通費)の移動をするにも拘わらず、
・労災保険の給付基礎日額(平均賃金)が増える
・雇用保険の賃金日額が増える
・社会保険料が増える可能性がある
・所得税が発生しかねないことになり、
所得税および社会保険制度的に生活が安定せず不合理です。
以上を考慮すると、
少なくとも建設業における現場に行く交通費は、
すべて出張旅費として取り扱うべきだと思うのですが、
法的根拠に基づいたわかりやすい区別が欲しいところです。
<通勤は、住居と常時勤務する場所間の移動>
カラカマが調べた限りにおいては、
「通勤」と「出張」の違いについて、
明確に言及している法律は存在しませんでした。
ただし、
国家公務員に関する別々の法律ではありますが、
以下のとおり規定されています。
●人事院規則9-24(通勤手当)第2条
通勤:職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署との間を往復することをいう。
●国家公務員等の旅費に関する法律第2条
出張:職員が公務のため一時その(常時勤務する)在勤官署を離れて旅行することをいう。
国家公務員の例を参考にすると、
通勤とは、
「住居と常時勤務する場所間の移動」を意味し、
その移動のために支給されたものを「通勤手当」
と呼ぶのが正しいと言えそうです。
<出張とは、期間の定めがある一時的な勤務場所までの旅行>
「一時的に常時勤務する場所に行く。」という文章は、
日本語的に変ですよね?
「通勤」と「出張」のさかいめを判断する際に、
カラカマが注目したのは、『一時』というキーワード。
国家公務員の例を参考にすると、
出張とは、
「業務のために『一時』的にいつもと異なる勤務場所への移動」を意味し、
その移動のために支給されたものを「出張旅費」
と呼ぶのが正しいと言えそうです。
一時的とは、
「〇月〇日から〇月〇日まで、名古屋支店に出張。」や、
「〇〇ビル建設工事の仕事が終わるまで出張。」のように
期間が限定的な状況を指すと考えられますが、
これであれば日本語的に違和感がありません。
以上より、カラカマ、
「通勤」と「出張」のさかいめは、期間限定かどうか?である。
という結論に至りました!!!
通勤手当については、今回のテーマの他にも、
・通勤車両を貸与した場合、その車両費用は通勤手当に加算すべきか?
・副業している場合、通勤経路に重複区間があったらどうすべきか?
・出社と在宅勤務がちょうど半々だった場合、出社は通勤になるのか?
などの論点もあり、悩みは尽きません。
副業・兼業者の「通勤」については、こちらで深堀りしているので、
よろしかったらどうぞ。