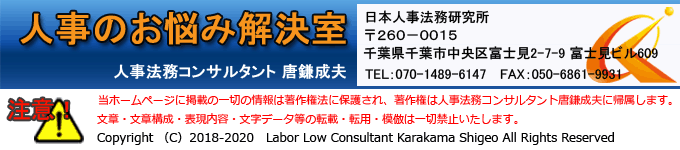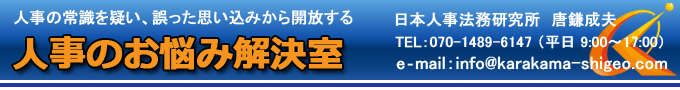
最終更新日:令和7年8月10日
社宅に入居する社員が退職した場合、
ほとんどの会社は、
特別な事情がない限り、遅滞なく退去してほしい
と考えるでしょう。
しかし、
社宅の賃貸借契約に借地借家法が適用された場合、
遅滞なく退去してもらえない恐れが生じます。
ここでは、
借地借家法の適用を回避するためには、
借上げ社宅の家賃はいくらに設定すべきか?
について、考えてみたいと思います。
※ここでは、自社保有社宅は検討の対象外とします。
<借地借家法とは?>
借地借家法は、その第30条(強行規定)に、
「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」
という規定があることからもわかるように、
家主が店子に合理的な理由もなく退去を強要することがないよう
借家に住む人の生活を守る規定が存在します。
同法第27条には、
「建物の賃貸人が賃貸借の解約をしたい場合、
6カ月以上前に解約の申し入れをしなければならない。」
という趣旨の規定があります。
社宅の賃貸借契約では、
「退職した場合、遅滞なく社宅を退去すること。」
と規定することが一般的ですが、
社宅の賃貸借契約に借地借家法第30条が適用された場合、
この特約が無効となり、申し入れ後6ヶ月間は退去を求められない
ことになりかねません。
<借地借家法を回避し得る家賃額は?>
雑誌「ビジネスガイド(令和7年8月号)」の記事によれば、
「・・・裁判例等に照らし、
従業員の負担割合を近隣の賃料相場の
数分の一から半分未満に設定していれば、
通常の賃貸借契約とは異なる特殊な契約と認められ、
借地借家法の適用は及ばないと考えられます。」
ということです。
令和4年の人事院の調査によれば、
民間企業の独身用借上げ社宅の全国平均は、
賃料(企業の契約額):64,309円
使用料(従業員の負担額):18,184円
であり、従業員の負担割合は約30%となります。
したがって、借地借家法の適用を避け、
退職時は遅滞なく社宅を退去してもらえる使用料は、
賃料の30〜50%程度と考えられます。
<国家公務員の官舎の家賃は?>
裁判官は、「特別職の国家公務員」なので、
国家機関等が所属する職員のために設置した宿舎である
「官舎」を使用する際には、「国家公務員宿舎法」
が適用されます。
とすれば、
「国家公務員宿舎法」に準じて社宅を運営しておけば、
借地借家法第30条が適用される可能性は極めて低い
とカラカマは考えたので「国家公務員宿舎法」を調べてみました。
国家公務員が退職した場合、
国家公務員宿舎法第18条の規定により、
20日以内に官舎から出ていかなければなりません。
有料宿舎の使用料(≒家賃)は、
国家公務員宿舎法施行令第13条に基づき計算されますが、
独身用官舎の場合、
東京23区でザックリ1.5万円程度、
地方部ではザックリ5千円程度の激安家賃のようです。
ちなみに、相当の事由があるとして、
所属する各省各庁の長の承認を受ければ、
無料宿舎であれば最長2カ月まで、
有料宿舎であれば最長6カ月まで、
住み続けることができるとされています。
<借上げ社宅の家賃はいくらに設定すべきか?>
国家公務員の官舎の使用料程度の社宅家賃であれば
99.9%借地借家法第30条の適用は回避できるでしょうか、
あまりに社宅の使用料が安いと社宅に入居していない社員から
不満が出かねません。
だからといって、
社宅に入居していない社員に対して、
定額の均衡手当を支給してしまうと、
労働法上、社宅が現物給与として賃金になりかねないので、
望ましくないでしょう
社宅入居中の社員が育児休業したら、会社の家賃負担はどうすべきか?参照
厚生労働大臣が定める現物給与の価額以上であれば、
社会保険料の算定基礎にならないことも考慮すると、
借上げ社宅の家賃はズバリ、
現物給与の価額以上かつ実際の賃料の30%程度が望ましく、
最大でも実際の賃料の50%までと考えます。
結論として、
独身⇒居室の広さが8畳の借り上げ社宅であれば、
●東京都の場合
・現物給与の価格:2,830円×8畳=22,640円
・賃料の相場:10万円程度(日経新聞の記事)
⇒23,000円〜30,000円程度
●千葉県の場合
・現物給与の価格:1,760円×8畳=14,080円
・賃料の相場:6万円程度(AIのGenimi調べ)
⇒15,000円〜18,000円程度
●横浜市の場合
・現物給与の価格:2,150円×8畳=17,200円
・賃料の相場:8万円程度(AIのGenimi調べ)
⇒18,000円〜24,000円程度
この程度の社宅家賃であれば、
借地借家法第30条は適用されず、
社員が退職した際は遅滞なく社宅を退去いただいても
問題ないと考えます。
余談ですが、所得税の場合は、
賃貸料相当額(次の1.から3.の合計額)の
50%以上の社宅家賃であれば、非課税になりますが、
異様に計算が面倒くさいです。
1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
2.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
3.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント