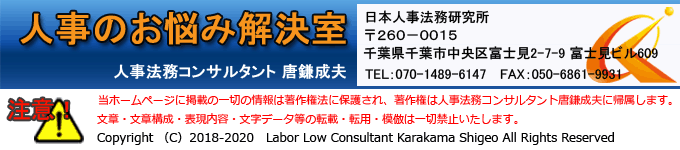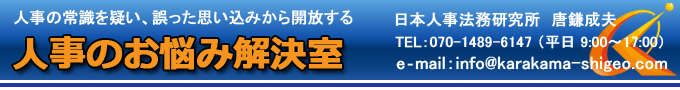
最終更新日:令和7年8月10日
36協定締結時に留意すべき事項について、
改めて検討してみた結果をシェアさせて頂きます。
【ポイント1:残業する理由には「等」を付ける】
36協定届には、
「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」
という欄があり、たとえば、
「受注の集中、納期の変更」などと記載します。
長期間企業を運営していれば、
36協定締結時には予想もしなかった事由、たとえば、
たまたま複数の社員が同時に退職したため、一時的に人員不足
となり、残業が必要になることもあるでしょう。
このような場合に、
「受注の集中、納期の変更『等』」と記載しておけば、
権利濫用にならない範囲である必要はありますが、
記載事項以外の事由であっても時間外労働を命じ得ると考えられます。
【ポイント2:特別条項の延長時間は月79時間以下にする】
時間外労働は、原則として月45時間が上限ですが、
特別条項を定めることにより、
臨時的に最長で月99時間まで延長が可能です。
時間外労働は、
安全・健康上望ましいことではないため、
延長することができる時間数があまりに長い場合、
労働基準監督署に注目され兼ねません。
・月60時間超の時間外労働の場合、割増率が50%になること。
・休日労働時間と合計して、複数月平均で80時間を超えないこと。
・休日労働時間と合計して、月100時間未満であること。
という法律の枠組みを考慮すると、
特別条項の延長時間は、以下に区分できそうです。
60時間以下の場合:穏当な範囲内であり、問題なさそう。
80時間以下の場合:ギリギリ健康を維持できる上限。
80時間超の場合:間違いなく監督署に目を付けられそう。
ある監督署では、
協定届に月80時間以上の延長時間が記載されている場合、
指導が行われると聞いたことがあります。
【ポイント3:実務上、対象期間は変更できるらしい】
「36協定あれこれ」では、やむを得ない事情がある場合を除き、
対象期間の起算日を変更できないとお伝えしました。
しかし、
社労士さんや顧問先での実例を考慮すると、
今回の対象期間が前回と重複していたとしても
届け出の際に問い合わせを受けることはないようです。
ただし、「改正労働基準法に関するQ&A」に、
「 36協定を再締結した後の期間においても、
再締結後の 36 協定を遵守することに加えて、
当初の36協定の対象期間における1年の延長時間
及び限度時間を 超えて労働さ せることができる月数
を引き続き遵守しなければなりません。」
とあるので、起算日を変更する際は注意しましょう。
【ポイント4:36協定の締結単位に注意】
36協定は、
労働基準法の適用単位である事業場毎に締結し、
それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署へ
届け出る必要があります。
ただし、一定の要件を満たす場合は、
各事業場の協定届をまとめて、本社を管轄する
労働基準監督署に一括して届け出ることができます。
注意が必要なこととして、
一括できるのは届け出という行政手続き行為のみであり、
全社員の過半数代表者を選出し、全事業所をまとめて
1つの協定で済ませることはできないという点です。
また、
「事業の単位」というテーマの1号店内の不動産屋(社員数6名)のように
主たる事業の一角で異なる零細事業を行っている場合、
零細事業の36協定を主たる事業の過半数代表者と締結
してしまっている会社を見かけますが、これはNGです。
【ポイント5:36協定と変形労働協定では届け出の意味が違う】
時間外労働は、
条文上、届け出行為が効力発生の要件となっており、
36協定届を労働基準監督署に届け出ることにより、
はじめて合法的に残業を命じることが可能となります。
36協定は「労使協定」の1種類なのですが、
1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制を
導入する場合も労使協定を締結する必要があります。
しかし、
変形労働時間制の労使協定は、36協定と異なり、
届け出行為は効力発生の要件ではありません。
したがって、
ウッカリ監督署へ届け出ることを忘れていた場合でも、
労働基準法違反で30万円以下の罰金刑に課される恐れはありますが、
民事上の法的効力は届け出の有無に左右されることはなく、
変形労働時間制の導入を否認されることはありません。